- 相続した遺産の総額が基礎控除額を上回らなければ、相続税はかかりません。
- ただし「配偶者控除」や「小規模宅地の特例」などを利用する場合は必ず申告が必要です。
- 土地の相続税評価額の求め方から相続税の計算方法まで確認し、相続税がかかりそうなら早めに対策していくことが大切です。
| 土地売却の第一ステップは査定! |
|---|
| 査定価格は不動産会社によって異なるもの。できる限り高値で売却するためには、複数社への査定依頼が鉄則です。不動産売却を考え始めたら、まずはあなたの不動産がいくらか一括査定で調べてみませんか? 一括査定を受けた方が良い理由は3つ! 1.相場を把握して適正価格で売却するため 2.査定額を比較できるため 3.相性の良い不動産会社に出会うため |
土地の一括査定依頼はこちらから無料
約2,300社の中から1番条件の良い不動産会社が見つかる!

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
目次
土地を相続すると相続税がかかるもの?
土地を相続したら、必ず相続税が課税されるわけではありません。相続税は、一定額以上の財産を相続したときに、課税対象になります。相続した遺産の総額が「基礎控除額」を上回らなければ相続税は非課税です。
相続税の計算をするときには、「基礎控除」のほかにも「配偶者控除」「小規模宅地等の特例」などのさまざまな控除制度があるので、控除制度を利用すれば非課税になるケースが多いです。亡くなった方のうち、実際に相続税が発生する割合は10人に1人程度です(2024年3月現在)。
土地の相続税を申告しなくてもよい場合とは
土地などの遺産の総額が「基礎控除額」を超えなければ、相続税は課税されないので申告の必要はありません。基礎控除額とは、被相続人の遺産総額から必ず控除できる金額のことで、計算式は以下のようになっています。
| 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
|---|
ここで注意したいのは、相続税はゼロでも申告が必要なケースがあるという点です。「基礎控除」は申告の必要がなく自動的に適用されますが、「配偶者控除」「小規模宅地等の特例」などは、相続税の申告をしないと控除を受けられません。
そのため、「遺産の総額が基礎控除を超えているけれど、各種控除を利用すれば相続税は非課税」というケースでは相続税の申告が必要です。
よりくわしい相続税の計算方法は、記事の後半でご説明します。まずは、相続の手続きについて押さえておきましょう。
相続手続きの流れ
2024年4月から相続登記が義務化されました
2024年4月1日よりも前に相続した不動産も、相続登記の義務化の対象です。正当な理由なく義務に違反すると、10万円以下の過料(ペナルティ)の対象となります。
相続が発生したら、相続人間で遺産の分割について早めに話し合いを行って、相続手続きを行いましょう。
土地の相続税評価額の計算方法
相続税評価額とは
土地の相続税評価額は、一般的に相続開始時点の換金価値(売却価格)よりも低い額となっていますので、その土地の価値以上に課税される心配は少ないです。
1.路線価方式による評価
路線価は、その道路に面する標準的な土地の1平米あたりの価値を千円単位で表記しており、1年に一度更新され、国税庁のホームページから簡単に確認することが可能です。路線価方式による評価額の計算式は以下のようになっています。
| 「正面路線価×各補正率(奥行価格補正率など)×面積」 |
|---|
2.倍率方式による評価
倍率方式を適用する土地は、郊外の土地や田畑、山林、原野などです。倍率方式による評価額の計算式は以下のようになっています。
| 「固定資産税評価額×倍率」 |
|---|
相続税の計算方法
【相続税の計算手順】
| 1. | すべての遺産額から借入金や葬儀費用を引いて、遺産総額を求める |
|---|---|
| 2. | 基礎控除額を引く |
| 3. | 相続税の総額を求める |
| 4. | 法定相続人ごとに相続税額を求める |
| 5. | 利用できる控除額を引く |
1.遺産総額を求める
これらのプラスの財産から、借入金や葬式費用などを差し引いて、遺産総額を求めます。
2.基礎控除額を引く
法定相続人の数を作為的に増やすことを防ぐために、2つのルールがあります。
1. 相続放棄者があった場合は、その放棄がなかったものとして法定相続人の数を数える。
2. 法定相続人のなかに養子がいるときは、次の数までしか法定相続人の数に算入できない。
| 実子がいる場合 | 普通養子は1人まで |
|---|---|
| 実子がいない場合 | 普通養子は2人まで |
3.相続税の総額を求める
課税遺産総額を法定相続分の割合どおりに取得したと仮定して、各法定相続人の取得金額を計算します。ここでは、実際の遺産分割ではなく、法定相続割合で計算するのがポイントです。
そして、各法定相続人の仮の取得金額に、下記の相続税率を乗じると、各相続人の相続税が算出できます。各相続人の相続税を合計すれば、相続税の総額が求められます。
| 各相続人の仮の取得金額=課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分 |
|---|
| 各相続人の相続税=仮の取得金額×税率―控除額 |
| 配偶者と子どもが相続人の場合 | 配偶者1/2、子ども1/2(2人以上のときは全員で分ける) |
|---|---|
| 配偶者と直系尊属が相続人の場合 | 配偶者2/3、直系尊属1/3(2人のときは全員で分ける) |
| 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(2人以上のときは全員で分ける) |
| 課税対象の遺産総額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
4.法定相続人ごとに相続税額を求める
計算式は次のとおりです。
| 各相続人の税額=相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額 |
|---|
控除・特例ので相続税の節税が可能
遺産が多いと多額の相続税がかかってしまいますが、相続税に関する控除を利用することで、相続税を軽減することが可能です。
以下の控除や特例を利用する場合には、納税がゼロになる場合でも相続税の申告が必要なのでご注意ください。それでは、主な控除について説明していきます。
配偶者控除
たとえば、夫が4億円の財産を配偶者と子に遺した場合、配偶者の法定相続分は2分の1の2億円です。この場合は1億6,000万円ではなく、2億円まで相続税が非課税にすることができます。配偶者は遺産相続で相続税が極力かからないよう配慮されているのです。
ただ、この制度を最大限利用して相続税を軽減するために、極力多くの財産を配偶者が相続したとしても、二次相続時の相続税が余計に多くなり、子に負担がかかる可能性もあります。
二次相続の相続税対策も合わせて、子と相続額の検討をするとよいでしょう。また、内縁の夫や妻は、この配偶者控除を受けることができませんのでご注意ください。
未成年者控除
| 満18歳になるまでの年数×10万円(1年未満の期間は切上げ) |
|---|
障碍者控除
控除額は2種類あり、一般障碍者か特別障碍者かによって分かれ、一般障碍者は、満85歳になるまでの年数×10万円、特別障碍者は、満85歳になるまでの年数1年×20万円を控除できます。なお、一般障碍者と特別障碍者の違いは以下のとおりです。
一般障碍者とは
・身体障碍者手帳上の障碍等級が3級~6級
・精神障碍者保健福祉手帳上の障碍等級が二級または三級
特別障碍者とは
・身体障碍者手帳上の障碍等級が1級または2級
・精神障碍者保健福祉手帳上の障碍等級が一級
贈与税額控除
つまり、7年以内の贈与を実質的な生前贈与とみなし、贈与税と相続税が二重にかかることを防いでくれる制度です。ただし、贈与時点で贈与税を支払っていない場合は、この控除の対象外となりますのでご注意ください。
相次相続控除
| 相次相続控除額=A×C÷(B-A)×D÷C×(10-E)÷10 |
|---|
A=相続1で支払った相続税
B=相続1でもらった財産価額
C=相続2における財産価額の合計額
D=相続2でもらう財産価額
E=相続1から相続2までの経過年数(1年未満は切り捨て)
たとえば、以下の条件で相続が2回行なわれたとします。
(例)
・A(相続1で支払った相続税)=1,000万円
・B(相続1でもらった財産価額)=1億円
・C(相続2における財産価額の合計額)=8,000万円
・D(相続2でもらう財産価額)=5,000万円
・E(相続1から相続2までの経過年数)=5年
この場合の相次相続控除額は、277万円となります。
また、もしA〜Dまでは同じ条件で、Eの経過年数が1年だった場合の控除額は500万円となり、前回の相続から日が浅いほど、控除額が多くなるのが特徴です。
なお、この控除を受けるには、1回目の相続で相続税を支払っていること、2回目の相続で法定相続人であることが条件となります。2回目の相続で相続人ではなく遺言で遺産を受け取った場合は、対象外となりますのでご注意ください。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住していた土地や事業をしていた土地に対し、80%または50%まで評価額を減額するものです。
対象となる宅地等は、「特定居住用宅地等」「特定事業用宅地等」「特定同族会社事業用宅地等」「貸付事業用宅地等」の4種類があります。今回はこのうち最も対象者が多い「特定居住用宅地等」についてご説明します。
「特定居住用宅地等」は、被相続人等が住んでいた宅地や、被相続人と生計をともにする親族が住んでいた宅地のことで、以下に当てはまれば評価額を軽減することが可能です。
| 【被相続人が住んでいた宅地】 |
|---|
| 被相続人の配偶者、同居していた親族が相続する場合。もしくは、被相続人に配偶者や同居する相続人がいない、その宅地に被相続人や配偶者が過去3年間居住していないときに、被相続人と同居していない親族が相続する場合。 |
| 【被相続人と生計をともにする親族が住んでいた宅地】 |
|---|
| 被相続人の配偶者や、被相続人と生計をともにする親族が相続する場合。 |
この特例は、自分も住んでいる住居を相続したときに、相続税が払えずに住居を売却するリスクを抑えるために定められています。なお、「生計をともにする親族」は、親族(配偶者、三親等内の姻族及び六親等内の血族)であればよく、相続人である必要はありません。
また、内縁の妻や夫に対して遺贈した場合は、この特例を適用することができません。
アパートなど賃貸住宅なら大幅に評価額が下がります
相続税の計算事例
計算順序は以下のようになります。
| 【ステップ1】 | 遺産総額を求める(←小規模宅地等の特例はここで活用) |
|---|---|
| 【ステップ2】 | 基礎控除額を引く |
| 【ステップ3】 | 相続税の総額を求める |
| 【ステップ4】 | 法定相続人ごとに相続税額を求める |
| 【ステップ5】 | 利用できる控除額を引く(←配偶者控除等はここで活用) |
【ステップ1】遺産総額を求める(計算例)
・現金や預金が4,000万円
・評価額5,000万円の土地
・借入金400万円
・葬儀費用200万円
遺産総額は、4,000万円+5,000万円-400万円-200万円=8,400万円
【ステップ2】基礎控除額を引く(計算例)
法定相続人が3人(妻、長男、長女)とすると、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。遺産総額から基礎控除額を引いて、8,400万円-4,800万円=3,600万円が課税遺産総額です。
【ステップ3】相続税の総額を求める(計算例)
妻:3,600万円×1/2=1,800万円
長男:3,600万円×1/4=900万円
長女:3,600万円×1/4=900万円
速算表で相続税額を計算すると、次のとおりです。
妻:1,800万円×15%-50万円(控除額)=220万円
長男:900万円×10%=90万円
長女:900万円×10%=90万円
相続税の総額は、220万円+90万円+90万円=400万円
【ステップ4】法定相続人ごとに相続税額を求める(計算例)
妻:400万円×40%=160万円
長男:400万円×30%=120万円
長女:400万円×30%=120万円
【ステップ5】利用できる控除額を引く(計算例)
なお、各種控除を利用すれば相続税がゼロになる場合でも、相続税の申告は必要です。
| スマイティが提携している一括査定サービスは無料で簡単に査定価格がわかる! |
|---|
| 1.WEB上で簡単な情報を入力するだけ! 2.最大6社まで一度に査定依頼することが可能! 3.依頼完了後、翌日~1週間ほどで結果が届く! |
土地の一括査定依頼はこちらから無料

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
相続税の申告期限と手続き
申告期限は10カ月以内
間に合わない場合は、未分割申告で対応することができます。未分割申告とは、協議がまとまっていなくても法定相続割合で分割したとして仮定して相続税を納付する方法です。その後、協議がまとまった時点で修正申告を行い、相続税の過不足分を処理します。くわしくは、国税庁のホームページで確認しておきましょう。
また、相続税の計算違いにより納税額に過不足があった場合は、修正申告が必要になります。修正申告を行った上で、税額が多かった場合は返金をしてもらい、不足していた場合は追加で納税が必要です。
追加で納税する場合は滞納とみなされ、延滞税が課せられます。せっかく期限内に申告・納税をしていても、税額が間違っていればペナルティとなってしまうため、不安が残る場合は税理士に相談するとよいでしょう。
相続した土地を売却するなら3年10カ月以内に
売れた際には仲介手数料などの経費、譲渡所得課税や印紙税などの税金がかかりますが、土地は持っているだけでコストがかかりますので、利用予定がなければ売却を視野に入れましょう。
また、相続した土地の売却に関する税制上の優遇措置もあり、相続税の申告期限から3年以内の売却であれば税負担が軽くなります。さらに、相続した居住用家屋及び敷地土地の売却時にかかる譲渡所得は、2016年4月1日から2027年12月31日までの間、条件付きで3,000万円まで軽減できる大きな優遇も受けることが可能です。
これらの優遇の利用を視野に入れて、売却活動をするとよいでしょう。
居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例は、適用期限が4年間延長され、適用要件も緩和されて利用しやすくなりました。

相続放棄をするなら3カ月以内に
裁判所への申し立てを行うためには、相続放棄の申述書や被相続人の住民票除票など多くの必要書類を揃えなければならず、早めの対応が必要です。期限内に書類の提出が間に合わなそうなとき、正当な理由があれば期間伸長の申立が可能です。
万一、3か月を過ぎてしまうと相続放棄を行うことができなくなります。ただし、借金の存在を後から知った場合に、やむを得ない事情があると認められれば例外的に期限後の相続放棄が認められる可能性もあります。
まとめ
| スマイティの一括査定サービスはHOME4Uと提携 |
|---|
| HOME4Uの特徴は以下の3つ。 1.実績豊富な一括査定サイト 2001年開始の日本で初めての一括査定サービス。“最大6社”に一括で査定依頼が可能。 2.2,300社の企業と提携 実績のある大手と地域密着型の不動産会社等、様々な得意分野を持つ約2,300社と提携。 3.NTTデータ・スマートソーシングが運営 情報サービス事業で業界大手のNTTデータグループが運営。 |
土地の一括査定依頼はこちらから無料

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
不動産売却の一括査定はこちらから
この記事の監修者

不動産鑑定士/土地活用プランナー
千葉大学卒業、地方銀行に勤務後、都内の不動産鑑定業者で事務所ビルやマンション等の収益物件の評価を数多く経験。現在は不動産鑑定士事務所を経営し、住宅・店舗・更地・山林・資材置場など多様な不動産に携わる。
土地活用や相続対策にも精通し、不動産に関するお悩み解決に尽力している。









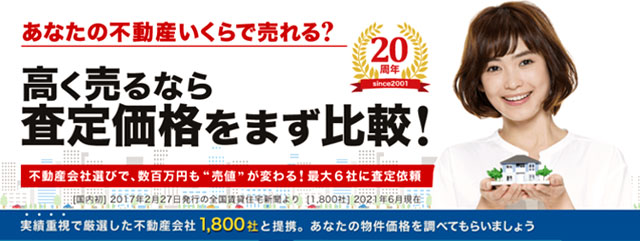


配偶者控除等は最後に【ステップ5】で差し引くことになっており、基礎控除と同時に差し引いたりすると誤った計算になってしまうので注意しましょう。