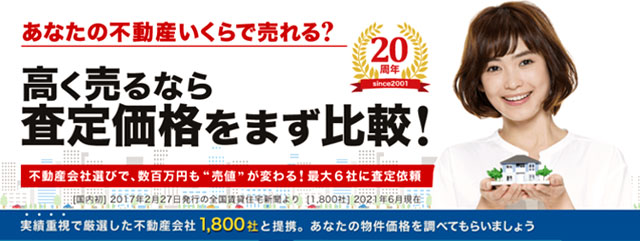- 3,000万円特別控除とは、不動産を売却した際に出た利益に対し3,000万円までは課税対象から除外できるというもの。
- 特別控除・特例を受けるためには確定申告が必須!確定申告書、譲渡所得の内訳書、住民票の写しなど書類の準備は忘れずに。
- どの特例が適用され、どのくらい税金が減額されるのか?不動産売却の前に調べておくことが大切です。
家の売却を検討中のあなたへ

不動産の一括査定依頼はこちらから無料
約2,500社の中から1番条件の良い不動産会社が見つかる!

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
目次
家や土地を売って利益が出ると譲渡所得税が発生する
不動産売却における税金について詳細はここでは割愛しますが、以下のページで説明していますので、詳しく知りたい方は合わせて確認してみてください。
譲渡所得の計算方法
| 譲渡所得=譲渡価格-(取得費+売却費用) |
|---|
たとえば、売却価格が3,000万円のとき、その不動産を取得する際に要した費用が1,000万円、売却に要した費用が100万円だった場合、課税譲渡所得は1,900万円となります。
短期譲渡所得と長期譲渡所得
不動産の譲渡所得に関する税率は所有期間によって異なります。不動産を売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下であれば、短期譲渡所得で39.63%(所得税30.63%、住民税9%)、5年超であれば長期譲渡所得で20.315%(所得税15.315%、住民税5%)です。
譲渡所得税が抑えられる?3つの特別控除・特例
上記で説明した例を元に計算してみましょう。仮に、平成20年5月1日に購入した不動産を、平成26年4月1日に売却したのであれば、所有期間は5年超(=長期譲渡所得)となりますので、税金は以下のように計算ができます。
| 1,900万円×20.315%=約386万円 |
|---|
1. マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円特別控除の特例
2. 10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
本特例の適用を受けられると、課税譲渡所得6,000万円まで税金を14.21%(所得税10.21%、住民税4%)とすることができます。
3. 特定の居住用財産の買換え特例
本特例の適用を受けると、売却価格のうち、新しくマイホームを購入した価格と同額部分の課税が繰り延べられます。つまり、3,000万円で売却して、4,000万円のマイホームを購入したときは、売却時の譲渡所得税は繰り延べられるため、税額は0円となります。
ただし、上手に使えば大きなメリットが得られますが、あくまでも次回に課税が繰り延べられるだけのため、よく考えて利用する必要があります。
特別控除・特例の要件
特別控除・特例を受けるための要件は以下のうち、どれかを満たしていることです。いずれも「居住用財産」、つまり、マイホームの売却である必要があります。
・現在、主として住んでいる自宅であること
・居住しなくなった日から3年後の年末までに売却すること
・建物を解体する場合は、上記の範囲内で、解体から1年以内に土地の売却契約を締結すること
・単身赴任の場合は配偶者の住んでいる建物も認められる
売却益が多ければ、その分税額が上がる場合も。
不動産の査定額を確かめてみましょう。
不動産の一括査定依頼はこちらから無料

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
3,000万円特別控除とは
先に計算した事例(売却価格3,000万、その不動産を取得する際に要した費用1,000万円、売却に要した費用100万)で、3,000万円特別控除の適用を受けられたとすると、下表1のように税額が0円となります。また、同じ不動産を7,000万円で売却できたとすると、下表2のようになります。
※()税額は、譲渡所得×20.315%で計算
| 表1 | |
|---|---|
| 譲渡価格 | 3,000万円 |
| 取得費 | -1,000万円 |
| 売却費用 | -100万円 |
| 特別控除 | -3,000万円 |
| 譲渡所得税(※) | 0円 |
| 表2 | ||
|---|---|---|
| 特例適用なし | 特例適用あり | |
| 譲渡価格 | 7,000万円 | 7,000万円 |
| 取得費 | -1,000万円 | -1,000万円 |
| 売却費用 | -100万円 | -100万円 |
| 特別控除 | 0万円 | -3,000万円 |
| 譲渡所得税(※) | 約1,199万円 | 約589万円 |
家を売るときは、まずは居住用財産の定義に当てはまるかどうか確認し、3,000万円特別控除を受けられるかを確認すると良いでしょう。
税控除や特例の要件にあてはまるのか、
プロにアドバイスを求めてみるのも◎。
不動産の一括査定依頼はこちらから無料

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
不動産売却で損失が出たときに受けられる2つの特例
1. 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
たとえば、2,000万円で売却した不動産が取得費として3,000万円、譲渡費用として100万円かかっていた場合には1,100万円の損失ですが、本特例の適用を受けることで300万円の給与所得など、他の所得と損益通算できます。
| 譲渡損失 | 2,000万円-(3,000万円-100万円)=-1,100万円 |
|---|---|
| 損益通算 | -1,100万円-300万円(給与所得)=-800万円 |
そして、平成30年には100万円に対する所得税、住民税を支払う必要があることになります。
| 損益通算 | 譲渡損失 | |
|---|---|---|
| 平成27年 | -1,100万円-300万円(給与所得) | -800万円 |
| 平成28年 | -800万円-300万円(給与所得) | -500万円 |
| 平成29年 | -500万円-300万円(給与所得) | -200万円 |
| 平成30年 | -200万円-300万円(給与所得) | 100万円 |
2. 居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
本特例との違いは、「売却する不動産に一定額以上の住宅ローン残高があること」と、「買換え資産の購入」が要件となっていないことです。
譲渡税控除の特例の要件に当てはまるなら
いまが売却のタイミングと捉えてもよいでしょう。
不動産の一括査定依頼はこちらから無料

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
そのほかの特別控除・特例
1. 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
2. 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例
3. 公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例
4. 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例
5. 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例
6. 農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例
特別控除・特例を受けるための手続き方法と必要書類
手続きのための確定申告は必ず行いましょう
よくある質問
- 特別控除や特例が受けられない場合ってどんなとき?
- 特別控除や特例は、併用・重複すると適用されないことがあります。たとえば、3,000万円特別控除と特定の居住用財産の買換え特例は併用できません。また、3,000万円特別控除、特定の居住用財産の買換え特例共に、住宅ローン控除との重複適用ができません。
売却不動産を購入したときに、住宅ローン控除の適用を受けている場合は、住宅ローン控除の終わる10年以内の売却だと重複する可能性があるため気を付けましょう。 - 特別控除・特例の併用ってできるの?
- ほとんどの場合、特別控除・特例の併用はできませんが、中には併用できるものもあります。たとえば、3,000万円特別控除と10年超の居住用財産の特例の併用です。3,000万円の特別控除を受けた後の課税譲渡所得に対して、課される税率を低くできるため、大きな節税につながります。
- 3,000万円特別控除って繰り返し適用できるの?
- 3,000万円特別控除は繰り返し適用することが可能です。ただし、前年、前々年に受けていないことが条件になります。3,000万円特別控除を受ける場合は、前年、前々年に適用されていないことを確認してから申請するようにしましょう。なお、10年超の居住用財産の特例についても重複適用が可能です。
- 店舗併用住宅を売却したときも3000万円特別控除が適用できる?
- 店舗住宅併用の場合でも3,000万円特別控除は適用されます。ただし、店舗併用住宅のうち居住の用に使っていた部分に限る、というのが条件です。
なお、居住の用に使っていた部分が全体の90%以上を占める場合は、全体を居住の用に使っていたものとして特例を受けることができます。
まとめ
事前に、どの特例の適用を受けることができ、どの特例を受ければ税額はいくらかを計算し、よりお得になる方法を選択するようにしましょう。
家を売って利益が出ると税金を支払う必要がありますが、
条件によって控除や特例を受けられます。
不動産の一括査定依頼はこちらから無料
約2,500社の中から1番条件の良い不動産会社が見つかる!

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
不動産売却の一括査定はこちらから
この記事の監修者

AFP/2級FP技能士/宅地建物取引士/相続管理士
明治学院大学 経済学部 国際経営学科にてマーケティングを専攻。大学在学中に2級FP技能士資格を取得。大学卒業後は地元の地方銀行に入行し、窓口業務・渉外業務の経験を経て、2011年9月より父親の経営する住宅会社に入社し、住宅新築や土地仕入れ、造成、不動産売買に携わる。