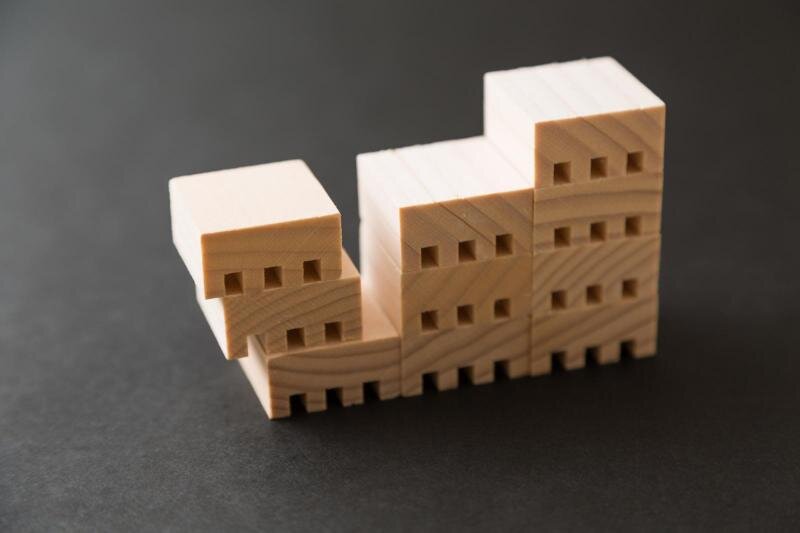- 分譲マンションを空き家の状態にした場合でも、管理費や固定資産税など年間34万円程度の支出が必要になります。
- 相続した分譲マンションが築40年を超えていたら買い手が付きづらい可能性も…。その場合は買取も視野に入れて。
- 相続発生から、相続をするか否かを考える期間は3か月です。相続発生前からあらかじめ家族間で話し合っておきましょう。
| マンション売却の第一ステップは査定! |
|---|
| 査定価格は不動産会社によって異なるもの。できる限り高値で売却するためには、複数社への査定依頼が鉄則です。不動産売却を考え始めたら、まずはあなたの不動産がいくらか一括査定で調べてみませんか? 一括査定を受けた方が良い理由は3つ! 1.相場を把握して適正価格で売却するため 2.査定額を比較できるため 3.相性の良い不動産会社に出会うため |
マンションの一括査定依頼はこちらから無料
約2,300社の中から1番条件の良い不動産会社が見つかる!

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
目次
親の古い分譲マンションは相続するべき?
親が所有する分譲マンションを相続するべきなのかは、どんな分譲マンションであるかにもよるところはありますが、築古分譲マンション、とくに築40年以上の分譲マンションは建物の老朽化のみならず、そこに住む人も老齢化が進んでいるケースもあります。それに伴って、分譲マンションの維持管理にも問題が生じている可能性もあるでしょう。
まずは、分譲マンションを相続するうえでの基本的なポイントについてご説明しながら、築古分譲マンションが直面する問題や、マンション相続後の活用方法について考えてまいります。
マンション相続に必要な手続きと税金の基礎知識
分譲マンション相続の流れ
① 遺言書の確認
ただし、相続人全員が遺言書の内容を変更することに同意する場合は、その限りではありません。
② 相続人の決定
相続放棄や相続欠格者、相続廃除者に子や孫がいる場合には、代襲相続が発生するため相続するか否か、意思の確認が必要になります。
③ 遺産分割協議書の作成
④ 相続税の申告・納付
しかし、相続税計算において特例等を利用した場合には、相続税の発生有無に関わらず、申告が必要になります。
⑤ 相続登記を行う
マンション相続にかかる税金
1.登録免許税
| 固定資産税評価額 × 0.4% = 登録免許税 |
|---|
相続税
| 基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数 |
|---|
【例】
夫が亡くなり、妻と子ども2人が夫の財産を相続した場合。
夫の財産は、預貯金3,000万円、分譲マンション2,200万円(※相続税評価)とする。
遺言書の「妻に預貯金1,000万円と分譲マンション、子に預貯金1,000万円ずつ相続する」という内容に従うものとする。なお、分譲マンションの敷地利用権について、小規模宅地の特例が使える場合があるが、今回は考慮しない。
預貯金3,000万円+分譲マンション2,200万円=5,200万円
●基礎控除
基礎控除額
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
遺産総額から基礎控除額を差し引く(課税対象額)
5,200万円-4,800万円=400万円
●課税対象額を法定相続分で按分
法定相続人は妻と子ども2人で、法定相続分は妻2分の1、子どもはそれぞれ4分の1。
妻:400万円×1/2=200万円
子:400万円×1/4=100万円
●税率をかけて、税額総額を出す
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ー |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
子: 100万円×10%=10万円
税額総額は、20万円+10万円+10万円=40万円
●遺産分割に応じて、各人の税額算出
妻の相続財産=預貯金1,000万円+分譲マンション2,200万円=3,200万円
相続財産総額に対する割合=3,200万円÷5,200万円≒0.6153
税額=40万円×0.6153=246,120円
ただし、配偶者の税額の軽減の適用を受けるため、税額は0円
相続財産総額に対する割合=1,000万円÷5,200万円≒0.1923
税額=40万円×0.1923=76,920円
相続したマンションの評価方法
| マンションの評価額=建物の評価額+土地(敷地利用権)の評価額 |
|---|
建物の相続税評価額は、固定資産税評価額と同じです。固定資産税評価額は、固定資産税の課税証明書、または固定資産評価証明書で確認できます。なお、この金額には、専有部分に対する評価額と共有部分の評価額に持分割合を乗じたものが含まれています。
【土地(敷地利用権)】
土地の相続税評価額を計算する方法には路線価方式と倍率方式の2種類があります。分譲マンションの所在地に路線価がある場合には路線価に分譲マンション全体の地積を乗じて算出します。その金額に持分割合を乗じると相続税評価額となります。
路線価がないエリアに立地している場合には倍率方式(固定資産税評価額に評価倍率を乗じる方法)で分譲マンション全体の評価額を算出し、その金額に持分割合を乗じて相続税評価額を求めます。
なお、分譲マンションの土地についても小規模宅地の特例が適用されます。
まずは資産価値をチェック
分譲マンションを相続するか否か、そして相続後にどのような選択肢(居住、売却、賃貸など)を選ぶのかは、あらかじめ資産価値を把握してから考えても遅くはありません。まずは、不動産会社に査定依頼をしてみてはいかがでしょう。
| スマイティが提携している一括査定サービスは無料で簡単に査定価格がわかる! |
|---|
| 1.WEB上で簡単な情報を入力するだけ! 2.最大6社まで一度に査定依頼することが可能! 3.依頼完了後、翌日~1週間ほどで結果が届く! |
マンションの一括査定依頼はこちらから無料

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
築古分譲マンションが直面する問題とは
分譲マンション飽和時代が来ている
分譲マンションを相続し、売却や賃貸の選択肢を検討する方もあると思います。しかし、2001年以降に建築された、比較的新しい分譲マンションが3割超ある中で、築40年以上の分譲マンションを選んでもらうために、どのような工夫が必要となってくるのかを考えるべきでしょう。
築古分譲マンションの維持費はこれだけかかる
分譲マンションの物件規模や共用施設、管理会社によっても異なりますが、築10年程度で管理費、修繕積立金がそれぞれ1万円、固定資産税が10万円程度はかかるのが一般的でしょう。つまり、住まないまま空き家にしたとしても、年間34万円程度の支出が必要になる可能性があるといえます。
さらに築古物件となると、それ以上の支出も考えられます。相続する可能性のある分譲マンションの管理費、修繕積立金、固定資産税について確認しておきましょう。
建て替え・修繕の問題
しかし、建て替えや大規模修繕には、分譲マンションの住人(所有者)の一定割合の同意も必要です。分譲マンションの住人(所有者)の高齢化が進んでいると、その一時金を支払えないため、建て替えや大規模修繕に同意を得られないケースもあります。
そのため建て替えや大規模修繕を実行することができず、維持管理に限界がきてしまった「限界分譲マンション」も増えているのが現状です。
相続放棄されるとどうなる?
また、仮に相続放棄をした後も、マンションの売却やその売却益などの国庫納付などを行う相続財産管理人が決まるまでは、管理義務は残ります。
また、相続放棄されたマンションに対して、相続財産管理人が選任されるまで管理組合は、何もできません。そのため、管理費や修繕積立金などが徴収できない状態が続く可能性もあり、管理組合会計が悪化することでマンション管理に支障が生じることになります。
マンションを相続した後の3つの選択肢と注意点
相続した分譲マンションに「住む」なら
管理体制が整っているかどうか
資産価値が下がらないかどうか
また、築古マンションの場合、大規模修繕等を行えず、新耐震基準を満たしていないケースもあります。長期修繕計画通りに修繕等を行い、資産価値を維持できる状況にあるかどうかの確認も重要です。
相続した分譲マンションを「貸す」なら
空き家のままよりも管理しやすく、家賃収入で固定費の支払いも可能になります。相続した分譲マンションを「貸す」ことを選択する場合、次のような点に留意が必要です。
賃貸物件として収支計画が成り立つかどうか
その収支計画を実現するための家賃設定が可能なのか、周辺の類似物件の家賃相場やニーズを確認しておく必要があります。
出口戦略を定めておく
何年間所有して、その後どうするのかあらかじめ考えておくことが望ましいでしょう。
相続した分譲マンションを「売る」なら
相続問題があると売却できない
しかし、時が経過し、元々の相続人の子や孫などが共有者になると話し合いの機会を持つことも難しくなります。分譲マンションを「売る」選択をする場合には、共有ではなく単独相続が望ましいでしょう。
買取も視野に入れて
不動産会社による買取も視野に入れながら、分譲マンションを「売る」姿勢を持っておきましょう。
マンション買取は業者探しがポイント!
一括買取査定なら手間なく複数業者に依頼できます。
※リビンマッチ不動産買取ページへ進みます
相続した分譲マンションは放置せず適切な判断を
分譲マンションを相続するのか否か、相続する場合にはどのような選択肢を選ぶのか、相続発生前からあらかじめ家族間で話し合っておく機会を設けておくようおすすめします。
まとめ
しかし、その間に、その問題がさらに進行し、選択肢が限られてしまう可能性もあります。将来的に分譲マンションを相続する可能性がある場合には、前もってどのようにするのかを家族間で話し合い、いざ相続が発生した時に慌てず対応ができるようにしておきたいものですね。
| スマイティの一括査定サービスはHOME4Uと提携 |
|---|
| HOME4Uの特徴は以下の3つ。 1.実績豊富な一括査定サイト 2001年開始の日本で初めての一括査定サービス。“最大6社”に一括で査定依頼が可能。 2.2,300社の企業と提携 実績のある大手と地域密着型の不動産会社等、様々な得意分野を持つ約2,300社と提携。 3.NTTデータ・スマートソーシングが運営 情報サービス事業で業界大手のNTTデータグループが運営。 |
マンションの一括査定依頼はこちらから無料
約2,300社の中から1番条件の良い不動産会社が見つかる!

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
この記事の監修者

AFP/社会福祉士/宅地建物取引士/金融広報アドバイザー
日本社会事業大学 社会福祉学部にて福祉行政を学ぶ。大学在学中にAFP(ファイナンシャルプランナー)、社会福祉士を取得。大学卒業後、アメリカンファミリー保険会社での保険営業を経て、(マンションデベロッパー)にてマンション営業、マンション営業企画に携わった。その後、2008年8月より独立し、現在、自社の代表を務める。