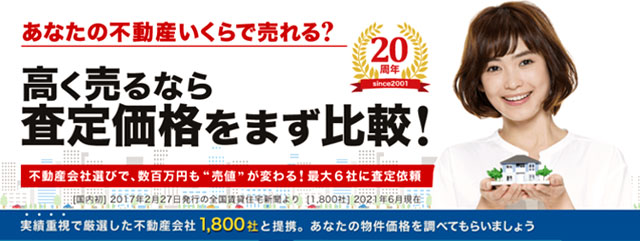- 「親族間売買」とは親と子など親族の間で不動産を売買すること。
- 条件を満たせば親族間売買でも特例・控除は受けられます!
- 親族間売買で失敗しないためには「適正価格を意識すること」「専門家に相談すること」が大切です。
| 不動産売却の第一ステップは査定! |
|---|
| 査定価格は不動産会社によって異なるもの。できる限り高値で売却するためには、複数社への査定依頼が鉄則です。不動産売却を考え始めたら、まずはあなたの不動産がいくらか一括査定で調べてみませんか? 一括査定を受けた方が良い理由は3つ! 1.相場を把握して適正価格で売却するため 2.査定額を比較できるため 3.相性の良い不動産会社に出会うため |
不動産の一括査定依頼はこちらから無料
約2,300社の中から1番条件の良い不動産会社が見つかる!

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
目次
親族間売買とは
というのも、親族間での不動産名義移転を目的とした場合、不動産を「贈与」するとその不動産の資産価値に応じて贈与者が贈与税を支払わないといけないため、「売買」したことにして税金を安くしようと考える可能性があるからです。
不動産の売買の場合、取引価格は買主と売主で自由に決めることができるため、本来は贈与を考えていたのにも関わらず、相場よりずっと安い価格で売買することが考えられます。なお、「売買」とは金銭を支払って不動産を取り引きすること、「贈与」は金銭を受け取らずに不動産を引き渡すことと考えるとよいでしょう。
ほかにも、親族間であれば所有者が死亡したときに、その子など相続人に対して資産が引き継がれる「相続」という方法もあります。それぞれの方法のメリット・デメリットを大まかに把握し、どの方法がベストかを比較検討する必要があります。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 親族間売買 | ・いつでも可能 ・売る側に売却金が得られる | ・相続より税金などの費用が高い場合がある ・買う側に資金が必要 |
| 生前贈与 | ・いつでも可能 | ・贈与税が発生する |
| 相続 | ・費用が押さえられる | ・所有者が亡くなるまで不可能 ・相続税が発生する ・法定相続人以外は遺贈となり税金が異なる |
親族の範囲とは
厳しく確認されるのは、相続税や贈与税逃れのための不動産売買に該当しないかどうか。したがって相続人に該当する親族か否か、が親族間売買の親族の概念に当てはまると考えていいかもしれません。
親族間売買と一般的な不動産売買の違い
仲介手数料が不要
ですが、親族間売買であれば、そうしたトラブルの心配もする必要がないため、不動産会社を利用する必要性は少ないでしょう。
ただし、親族間売買であっても、税金の手続などの関係から、不動産売買契約書を作成する必要があり、これを自分で用意する必要があるという問題はあります。
売却価格が低いとみなし贈与となる
たとえば、時価2,000万円の物件を800万円で売却した場合、時価と売却額の差額である1,200万円がみなし贈与と判断される可能性があります。時価から引き下げた分の価格を金銭で贈与したとイメージすると分かりやすいでしょう。なお、みなし贈与については相続税法の第七条に以下のように記載されています。
七条
著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
上記の通り、みなし贈与と判断されるかどうかは不動産の「時価」と売買額の差額によります。時価を調べるには不動産の「路線価」を調べたり、不動産鑑定士への鑑定依頼や不動産会社に査定依頼を出したりといった方法が考えられます。
時価を把握したうえで、どの程度の差額までであれば許容されるかなどについては、税理士などの専門家に相談すると万全です。
税金の控除や特例が使えない
・買主が売主の配偶者及び直系血族
・買主が売主の親族でその個人と生計を一にしているもの及び買主が売主の親族でその譲渡にかかる家屋の譲渡がされた後その家屋に居住するもの
とくに、マイホームを売却した際に譲渡所得から3000万円を控除できる特例が適用外になるため、譲渡所得税が高額になる恐れがあります。
住宅ローンの審査が厳しい
金利の安い住宅ローンをほかの用途に不正利用したり、借金の付け替えを目的とするような不適切な借り換えで住宅ローンを組まれることを恐れているため、親族間売買での融資は行わないという金融機関もあるのが事実です。
とくに築年数の経った古い実家を売買するようなケースでは、融資の審査が通りにくく、住宅ローンが組めないといった問題が起こりやすい点にも注意が必要です。
| スマイティが提携している一括査定サービスは無料で簡単に査定価格がわかる! |
|---|
| 1.WEB上で簡単な情報を入力するだけ! 2.最大6社まで一度に査定依頼することが可能! 3.依頼完了後、翌日~1週間ほどで結果が届く! |
不動産の一括査定依頼はこちらから無料

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
親族間売買の流れ
次に、売買価格を決定しますが、売買価格については先述の通り、みなし贈与とならないよう時価を調べたうえで、必要に応じて税理士等専門家に相談することが大切です。
売買価格が決まったら、先に取得した登記簿謄本の内容と売買価格を記載した不動産売買契約書を作成します。不動産売買契約書については、不動産会社も利用する全宅連の不動産売買契約書など、インターネットでテンプレートをダウンロードできます。
売買契約書を取り交わしたら、買主側が住宅ローンを利用する場合は金融機関と日程を決めてローンを決済し、売主に代金を支払います。できれば代金の授受は銀行振り込みで行い、客観的に金銭の受け渡しがあったことを証明できるようにしておきましょう。
また、決済と同時に所有権移転登記を行いますが、こうした登記手続きについては司法書士に依頼する必要があります。親族間売買で不動産会社を利用しない場合、金融機関や司法書士とのスケジュール調整をするのはすべてご自身となるので、注意が必要です。
適正価格の設定方法
著しく低い価格で売買したとみなされないようにするためには、通常の売買に準じた適正価格は以下のような方法で求める必要があります。
・不動産会社の査定による価格
・不動産鑑定による価格
・路線価より求めた価格
① 路線価×1.25で実勢価格を求める方法
② 路線価をそのまま使う方法
路線価は地価公示価格の80%を基準として定められるため、実勢価格よりやや低い価格であるといえます。しかし、路線価そのままを利用した価格設定で親族間売買を行った場合も、著しく低い価額での譲渡には当たらないとした過去の判例があります(東京地方裁判所平成19年8月23日判決、平成18年(行ウ)第562号)。
また、売買価格の設定だけでなく、借金の肩代わりを条件とした不動産の親族間売買や、持分割合と売買価格の比率が噛み合わない場合なども、税務署からお訊ねが来るかもしれません。税理士など第三者の客観的なアドバイスを求めると万全です。
親族間売買の税金と利用できる控除・特例
売る側にかかる税金
不動産の譲渡所得税とは、不動産を売却して得た利益に対して課されるもので、売却したときに要した経費や、売却する不動産を取得したときに要した経費などを、売却価格から差し引くことができます。
たとえば、不動産を1,000万円で売却して、経費が200万円だった場合、差額の800万円に対して税金が課されることになります。なお、譲渡所得税の税率は以下のようになっています。
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 10.315% | 5% | 15.315% |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
なお、不動産の譲渡所得税以外にも、売買契約書に貼り付けする印紙税や、登記簿謄本に記載の住所が実際の住所と異なる場合には登録免許税も納める必要があります。
買う側にかかる税金
不動産取得税の税率は固定資産税評価額×3%(2024年3月31日まで)となっており、そのほか新築日に応じて控除を受けられるようになっています。
| 新築日 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 1997年(平成9年) | 4月1日以降 | 1,200万円 |
| 1997年(平成9年) | 3月31日以前 | 1,000万円 |
| 1989年(平成元年) | 3月31日以前 | 450万円 |
| 1985年(昭和60年) | 6月30日以前 | 420万円 |
| 1981年(昭和56年) | 6月30日以前 | 350万円 |
| 1975年(昭和50年) | 12月31日以前 | 230万円 |
| 1972年(昭和47年) | 12月31日以前 | 150万円 |
| 1954年(昭和29年) | 7月1日 | 100万円 |
| 〜1963年(昭和38年) | 12月31日 | |
また、不動産を買うときと同様、売買契約書に貼り付けする印紙税や、登記時に支払う登録免許税などがかかります。
なお、不動産の売買では、所有権移転登記をする必要がありますが、この登記費用は、一般的に買主側が負担することが多いです。
親族間売買でも条件を満たせば受けられる特例
たとえば、4,000万円の住宅ローンを組んだ場合、4,000万円×1%×13年間=最大520万円分の控除を受けられる計算となります。住宅ローン控除については買主側や物件が条件を満たせば、親族間売買であっても利用可能です。
親族間売買を行う際の注意点
適正価格を意識し、売買契約書を必ず作成する
住宅ローンを利用しない場合でも、簡単なメモ書きのようなものでなく、きちんとした売買契約書を作成することをおすすめします。
税務署やほかの親族から売買取引を装った生前贈与を疑われないためにも、取引の条件や内容を示すことのできる正式な書類を残しておくべきでしょう。
部分的に専門家の手を借りる
しかし、みなし贈与とされないために売買価格の決定の際には税理士を利用するなど、部分的に専門家に相談することは大切です。
そのほか、不動産売買契約書の作成のみ不動産会社に依頼したり、登記手続きについて司法書士に依頼したりするなど、必要に応じて専門家に相談するとよいでしょう。
親族の同意を得る
「親族間売買」以外の選択肢と比較する
贈与税は売買でかかる税金よりも税率が高くなりますが、「相続時精算課税制度」を利用することで贈与時の課税額を軽減することが可能です。売買にこだわらず、どの方法が最善であるかを話し合う機会を持ちましょう。
よくある質問
- 住宅ローンが借りられない場合の他の選択肢はありますか?
- 親族間での不動産売買に対する住宅ローンは、金融機関の審査が非常に厳しくなっています。不動産担保ローンやプロパーローンが可能になるケースもありますが、満額に満たない場合や金利が高くなる可能性が高いでしょう。
ほかには分割払いを当事者同士で決め、契約を取り交わす方法もあります。 - 親族間売買でも不動産会社を介したら仲介手数料は満額必要?
- 不動産売買における仲介の役割として、売主・買主を探すこと、その間を取り持って正しく取引を遂行することがあります。親族間売買の場合、売主・買主は探す必要がなくスピーディーな取り引きが可能となるため、仲介手数料に関しても仲介の相談を持ち込む時点で交渉することは可能でしょう。
ただし、親族間売買は通常の売買とは異なった視点で、難しい取り引きであることは覚えておきましょう。
まとめ
そのほか、売買契約書の作成時には不動産会社を、登記手続き時には司法書士を頼るなど、部分的に専門家に相談しながら進めていくことをおすすめします。
| スマイティの一括査定サービスはHOME4Uと提携 |
|---|
| HOME4Uの特徴は以下の3つ。 1.実績豊富な一括査定サイト 2001年開始の日本で初めての一括査定サービス。“最大6社”に一括で査定依頼が可能。 2.2,300社の企業と提携 実績のある大手と地域密着型の不動産会社等、様々な得意分野を持つ約2,300社と提携。 3.NTTデータ・スマートソーシングが運営 情報サービス事業で業界大手のNTTデータグループが運営。 |
不動産の一括査定依頼はこちらから無料
約2,300社の中から1番条件の良い不動産会社が見つかる!

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
不動産売却の一括査定はこちらから
この記事の監修者

AFP/2級FP技能士/宅地建物取引士/相続管理士
明治学院大学 経済学部 国際経営学科にてマーケティングを専攻。大学在学中に2級FP技能士資格を取得。大学卒業後は地元の地方銀行に入行し、窓口業務・渉外業務の経験を経て、2011年9月より父親の経営する住宅会社に入社し、住宅新築や土地仕入れ、造成、不動産売買に携わる。