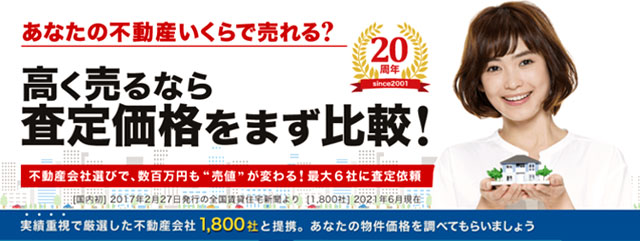- 不動産の個人間売買とは、売主・買主個人同士で不動産売買を完結させること。
- 個人間売買は仲介手数料がかからないなどのメリットがありますが、トラブルになりやすいなどのデメリットもあります。
- スムーズな不動産売買を目指すなら、不動産会社に仲介を依頼する方がよいでしょう。
| 不動産売却の第一ステップは査定! |
|---|
| 査定価格は不動産会社によって異なるもの。できる限り高値で売却するためには、複数社への査定依頼が鉄則です。不動産売却を考え始めたら、まずはあなたの不動産がいくらか一括査定で調べてみませんか? 一括査定を受けた方が良い理由は3つ! 1.相場を把握して適正価格で売却するため 2.査定額を比較できるため 3.相性の良い不動産会社に出会うため |
不動産の一括査定依頼はこちらから無料
約2,300社の中から1番条件の良い不動産会社が見つかる!

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
目次
不動産の個人間売買とは
一般的な不動産売買では、不動産業者が仲介に入って手続きをサポートしますが、個人間売買では、現地確認、契約交渉、契約書の作成・締結から引渡しまで、すべての手続きを個人が行います。
不動産の個人間売買に向いている人
他にも、
・所有地を隣人に売却する
・貸している土地を借主に売却する
・借地権者に相手の家が建っている底地を売却する
など、取引の相手方が既に決まっている場合にも個人間売買によって取引されることがあります。
また、山林や田舎の農地など、かなり低額な不動産の売買の場合には、仲介手数料が少額になってしまうために、不動産業者も仲介を敬遠する傾向があります。
また最近では、自治体が運営する「空き家バンク」などのインターネットサイトを利用して個人間売買を行う人も増えているようです。
不動産の個人間売買のメリット・デメリット
【メリット①】仲介手数料・消費税が不要
たとえば、3,000万円の不動産の取り引きならば、105万6,000円(税込)の仲介手数料を支払うことになりますが、個人間売買ではこの分が節約できますので、大きなメリットです。
【メリット②】調整がしやすい
不動産取引に時間がかかる理由の1つに、現地確認や内見、契約や引渡しのスケジュール調整、契約交渉のやり取りに時間がかかることが挙げられますが、個人間売買の場合には直接連絡を取り合うために、スムーズに手続きが進みやすいのです。
【デメリット①】トラブルになりやすい
とくに、建物の不具合や土地の面積に関する契約不適合責任や売買価格が相場と合わないことから生じるトラブルについては、解決が長引くことも多く、最悪の場合には契約解除に発展する可能性もあります。
仲介業者がいれば、双方の言い分を考慮して調整するところですが、当事者同士だとなかなか解決に進まないことも多いのです。
【デメリット②】住宅ローンが組みにくい
金融機関が取り扱う住宅ローンを組む時の必要書類として、宅建業者が作成した売買契約書・重要事項説明書が求められるのが一般的ですので、個人間の売買では住宅ローンの申請ができないことがあります。
【デメリット③】手間や時間がかかる
これらの手続きの負担は、買主よりも売主にかかってくることが多く、不動産取引に慣れていなければ、契約書の作成だけでも一苦労です。
| スマイティが提携している一括査定サービスは無料で簡単に査定価格がわかる! |
|---|
| 1.WEB上で簡単な情報を入力するだけ! 2.最大6社まで一度に査定依頼することが可能! 3.依頼完了後、翌日~1週間ほどで結果が届く! |
不動産の一括査定依頼はこちらから無料

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
個人間売買の手続きの流れ
それでは、売買の手続きの流れを見ていきましょう。
ステップ①売買金額を決める
取引相場は、民間の不動産情報サイトのほか、国土交通省が提供する不動産情報ライブラリで検索することが可能です。
ステップ②買主を探す
最近では、個人間売買向けのマッチングサイトがありますので、掲載を検討してみるのもよいかもしれません。
ステップ③売買契約を締結する
契約書類としては売買契約書のみで、重要事項説明書や媒介契約書の締結はありません。
ステップ④代金入金を確認する
地方銀行や信金・信組からメガバンク、あるいは逆への送金は時間がかかることがありますので、振込票の確認で入金確認に変えることもあります。
ステップ⑤引渡しを行う
すべてが終了したのち、売主に売買益が生じる場合には、確定申告を行うことも忘れてはなりません。特例を活用する時にも確定申告が必要になりますので、不安な場合には税理士に相談してみましょう。
個人間売買に必要な書類と契約書の作成方法
一般的な記載事項には以下のようなものがあります。
・売買の目的物および売買代金
・売買代金の支払いの時期、方法など
・売買対象面積、測量、代金精算
・所有権の移転の時期
・引渡しの時期
・抵当権等の抹消
・引渡し完了前の滅失、毀損
・公租公課等の分担
・契約違反による解除、違約金など
また、個人間の売買契約でも、売買代金に応じて契約書に印紙を貼付する必要があります。
印紙税額については、国税庁のサイトをご参照ください。
必要書類一覧
【必要書類の例】
| 書類名 | 入手場所 |
|---|---|
| 土地・建物登記済証(権利証)または登記識別情報 | 売主保管 |
| 登記簿謄本 | 所在地管轄の法務局 |
| 公図・測量図・建物図面等 | 所在地管轄の法務局 |
| 建築確認通知書・検査済証(建物がある場合) | 売主保管 |
| 固定資産税課税証明書 | 市区町村役場の担当課(固定資産税課など) |
| 固定資産税・都市計画税納税通知書 | 売主保管 |
| 印鑑証明書(3か月以内の発行のもの) | 市区町村窓口 |
| 本人確認書類(運転免許証・パスポートのコピーなど) | 売主保管 |
| 領収書 |
|---|
| 振込票のコピー |
| 印鑑証明書(3カ月以内の発行のもの) |
| 本人確認書類(運転免許証・パスポートのコピーなど) |
売買契約書の作成方法
建物の修繕や残置物の処理など、当事者間の特有の合意事項については、条項の最後に特約事項としてまとめておくとよいでしょう。
個人間売買の必要経費
印紙税
| 500万円超1,000万円以下の土地 | 10,000円 |
|---|---|
| 1,000万円超5,000万円以下の土地 | 20,000円 |
| 500万円超1,000万円以下の土地 | 5,000円 |
|---|---|
| 1,000万円超5,000万円以下の土地 | 10,000円 |
登録免許税
売主については、土地を売却するにあたり抵当権を抹消する必要がある場合のみ登録免許税が発生します。抵当権抹消登記の登録免許税額は、不動産1個につき1,000円です。
司法書士報酬
所有権移転登記に関しては2万円から10万円超とかなり幅がありますが、大体4万円前後が平均となっています。抵当権抹消登記については大体8千円から3万円の間で、1万5千円前後の場合が多いようです。
個人間売買のトラブルを防ぐ方法
相場を把握する
みなし贈与とは、時価よりもかなり安価な価格で売買された場合に、時価との差額を贈与したとみなされて贈与税が課されるというものです。この場合には、仲介手数料の費用減よりも高くついてしまう可能性がありますので、注意が必要です。
契約不適合責任を理解する
対象物件の築年数が古い、取得の経緯が明らかでないなどの場合には、売買金額を減額して、責任免除の規定を設けることもあります。いずれにせよ、売主としての責任を負っているということは十分に理解しておく必要があります。
登記などの手続きは司法書士に依頼する
司法書士は登記手続きを代行するだけではなく、売買が有効に成立しているかどうかの法的な検証も行いますので、その点についても安心感のある取り引きができます。
買主の見極めは慎重に行う
とくに新規に買主を探す場合には、柔軟な対処ができるかどうか確認のうえで取り引きをしましょう。
部分的に不動産会社に依頼する
よくある質問
- 個人間売買サイト利用の注意点は?
- 個人間売買サイトは最近開設されたものが多いために、提供サービスが固まっていないものが多くなっています。中には物件確認や本人確認なしに掲載されているものもあります。利用する際には、Webサービスでどこまで対応してもらえるのか、物件確認や本人確認が適切に行われているかチェックする必要があります。
- 仲介会社と個人間売買両方の可能性を探ることはできる?
- 仲介業者に依頼するのと個人間売買の両方を検討することは可能です。もし仲介業者が高値で購入してくれる買主を探してきたら、そちらと契約するといった具合です。その際には、仲介業者との媒介契約書の種類について、自己発見取引が可能である一般媒介もしくは専任媒介にしなければなりません。
- 不動産の個人間売買で支払う税金は?
- 個人間売買においても、印紙税、登録免許税、そして譲渡益が出た場合には売主に譲渡所得税の申告義務があります。売主は、確定申告で納税する譲渡所得税まで考えて資金計画を立てておいたほうがよいでしょう。
まとめ
例に挙げた仲介手数料はあくまでも「上限額」です。既に取引の相手が決まっているのであれば、仲介手数料をできるだけ抑えてもらうよう不動産会社に交渉することも可能でしょう。
後々のリスクを排除し、スムーズに取引を行うためにも、不動産売買は不動産会社の仲介で行う方がよいでしょう。その際、一括査定のサービスを利用して、複数社の中からより相談しやすい不動産会社を選択することをおすすめします。
| スマイティの一括査定サービスはHOME4Uと提携 |
|---|
| HOME4Uの特徴は以下の3つ。 1.実績豊富な一括査定サイト 2001年開始の日本で初めての一括査定サービス。“最大6社”に一括で査定依頼が可能。 2.2,300社の企業と提携 実績のある大手と地域密着型の不動産会社等、様々な得意分野を持つ約2,300社と提携。 3.NTTデータ・スマートソーシングが運営 情報サービス事業で業界大手のNTTデータグループが運営。 |
不動産の一括査定依頼はこちらから無料
約2,300社の中から1番条件の良い不動産会社が見つかる!

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
不動産売却の一括査定はこちらから
この記事の監修者

宅地建物取引士
株式会社イーアライアンス代表取締役社長。中央大学法学部を卒業後、戸建・アパート・マンション・投資用不動産の売買や、不動産ファンドの販売・運用を手掛ける。アメリカやフランスの海外不動産についても販売仲介業務の経験を持ち、現在は投資ファンドのマネジメントなども行っている。