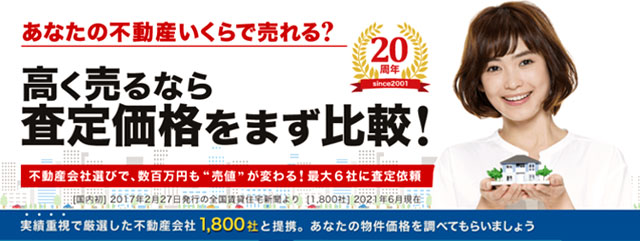- 年の途中で売却が成立した場合、売却~年末までの期間分の税額を日割り計算して買主に負担してもらうことが一般的。
- 住宅用地の特例、新築住宅の特例など、条件を満たすことで固定資産税が軽減される特例があります。
- 不動産を所有すると毎年支払うことになる固定資産税。仕組みを理解しておくことは大切です。
不動産の一括査定依頼はこちらから無料
約2,300社の中から1番条件の良い不動産会社が見つかる!

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
目次
固定資産税・都市計画税とは?
固定資産税とは
※償却資産:償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要経費に算入されるものを指します。つまり、一般的な自宅資産に付随する資産は対象となりませんので、参考までに留めておいて問題はありません。
固定資産税がかからない場合も
都市計画税とは
課税主体は市町村で、毎年1月1日現在の所有者に納税義務があります。課税標準は、固定資産税評価額で、原則としてその金額に税率0.3%(制限税率)を乗じて都市計画税額を算出します。
なお、固定資産税は、全ての土地と建物が対象となりますが、都市計画税は都市計画法による市街化区域内に所在する土地と建物が対象となります。また、市町村によっては課税されないケースもあります。
固定資産税・都市計画税の計算方法
固定資産税の計算方法
標準税率とは、地方税を課税する場合に、通常用いることとされている税率のことをいいます。財政上の特別の必要があると認める場合には、課税主体(市町村)の判断によって、標準税率と異なる税率を条例で定めることができます。
都市計画税の計算方法
制限税率とは、地方税を課税する場合に、課税主体(市町村)が課税することのできる税率の最高限度を制限するものです。つまり、都市計画税の場合は、税率が0.3%を超えることはないということになります。
固定資産税・都市計画税の発生時期と納付方法
発生はいつから?
納付時期はいつ?
固定資産税を滞納したら延滞金が発生する
納期限から1か月を超えてもなお、納付ができない場合には、税額に特例基準割合+7.3%を乗じた金額を延滞金として納める必要があり、さらに負担が増えることになります。
固定資産税や都市計画税の支払いが困難な場合には、早めに市町村の窓口で相談するようにしましょう。
※特例基準割合:各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均の割合に、年1%を加算した割合
支払う人は誰?
なお、売却した後の固定資産税・都市計画税は日割り清算になります。年の途中で売却が成立した場合には、売却から年末までの期間分の税額を日割り計算して、買主に税額負担してもらうことが一般的です。
固定資産税の支払いが難しい場合は売却を検討してみては?
まずは一括査定で相場を調べてみましょう!
不動産の一括査定依頼はこちらから無料
約2,300社の中から1番条件の良い不動産会社が見つかる!

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
固定資産税が軽減される特例
1. 住宅用地の特例
小規模住宅用地
一般住宅用地
マンションの小規模住宅用地の考え方
登記簿謄本の表題部の「敷地権の割合」を確認し、敷地全体のうち敷地利用権を有する面積を計算してみましょう。その面積が200 m2以下であれば、先述した小規模住宅用地の特例適用を受けられます。
2. 新築住宅の特例
なお、この特例は、床面積120m2相当分までの適用となり、120m2超相当分については、税額軽減の適用はありません。
3. 既存家屋の特例
省エネ改修
バリアフリー改修
耐震改修
4. 負担調整措置
それ以前は、公示価格よりも極めて低い水準で推移していたため、3年に1度の評価替え時に税負担が急増する可能性もありました。そうならないように、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置が講じられています。
負担水準
上記計算式で算出される負担水準が100%以上の場合は、課税標準額が据え置き、または引き下げとなります。一方、負担水準が100%未満の場合は、課税標準額が上昇します。
納付通知書と自治体の情報は必ず確認しましょう
また、固定資産税は地方税なので、自治体毎に優遇措置を設けている場合があります。情報を逃さないためにも自治体のホームページもチェックしておくとよいでしょう。
よくある質問
- 基準となる固定資産税評価額とは?
- 固定資産税評価額は、市町村によって決められます。実勢価格(不動産を売却する際の取引価格)の目安とされている公示価格の70%の水準となるように設定されています。
この固定資産税評価額は3年に1度、評価の見直しが行われます。詳しくは固定資産税評価額の記事を参照ください。 - 更地にすると固定資産税は6倍かかるって本当?
- 住宅用地には課税標準が軽減される特例がありますが、既存建物を取り壊した場合、更地となり、その特例の適用を受けられなくなります。
課税標準は本則にもどるため、特例適用を受けていた時と比較すると6倍の税額負担が生じる点には注意が必要です。詳しくは空き家の固定資産税の記事を参照ください。 - 固定資産税が払えないときに利用できる制度とは?
- 固定資産税が払えない事態になってしまったときに利用できる制度についても知っておきましょう。まずは、滞納処分の停止です。
一定の要件を満たすと滞納処分の停止が認められ、滞納している固定資産税の納税義務そのものが消滅します。その他、徴収の猶予や換価の猶予などがあります。詳しくは固定資産税滞納の記事を参照ください。
まとめ
不動産を所有すると毎年支払うことになる税金だからこそ、仕組みを理解しておくのは大切なことです。専門家のサポートも活用しながら理解に努めてみてはいかがでしょうか。
不動産所有には固定資産税と都市計画税がかかります。
条件によっては特例を受けられるので、必ず確認しましょう。
不動産の一括査定依頼はこちらから無料
約2,300社の中から1番条件の良い不動産会社が見つかる!

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
不動産売却の一括査定はこちらから
この記事の監修者

AFP/社会福祉士/宅地建物取引士/金融広報アドバイザー
日本社会事業大学 社会福祉学部にて福祉行政を学ぶ。大学在学中にAFP(ファイナンシャルプランナー)、社会福祉士を取得。大学卒業後、アメリカンファミリー保険会社での保険営業を経て、(マンションデベロッパー)にてマンション営業、マンション営業企画に携わった。その後、2008年8月より独立し、現在、自社の代表を務める。