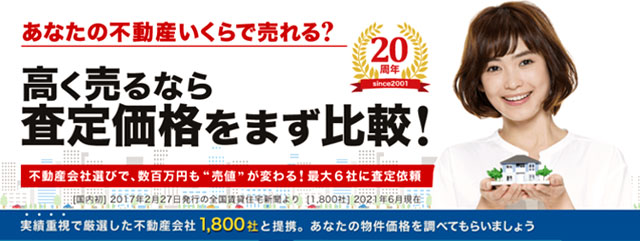不安になる前にプロに相談してみるのが、売却への第一歩です!
不動産の一括査定依頼はこちらから無料
約2,300社の中から1番条件の良い不動産会社が見つかる!

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
目次
契約不適合責任とは
民法第562条1項
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
つまり、実際に引渡しを受けたものが契約内容と異なる場合には、買主が売主に対して、責任追及(追完請求、代金減額請求、解除、損害賠償請求)を行えることを示しています。
瑕疵担保責任から契約不適合責任と変わった経緯
旧民法第570条
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
旧民法第566条
売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる
瑕疵担保責任の「瑕疵」とは、欠陥や問題を表す言葉です。しかし、この条文では「瑕疵」の内容がイメージしづらいため民法改正に際して、イメージのしやすい「契約不適合」という言葉が用いられました。
つまり改正によって、契約内容との不一致があった場合に責任追及ができることが明確になったわけです。
また、改正前は買主の権利も、損害賠償請求と解除ができるのみでしたが、買主が権利行使できる選択肢が増えた点も大きく変わったポイントといえるでしょう。
なお、「契約不適合」な点は「隠れた」ものである点は要件でなく、買主が事前に契約不適合である事実を知っていても売主の責任が生じるため、売主の責任はより大きくなったといえます。
買主が持つ5つの請求権利
なお、買主が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しない時は、各権利を行使できません。ただし、売主が「引渡しの時に契約不適合を知っていた時」または「重大な過失によって知らなかった時」には、買主から責任追及をされる可能性もあります。
1.追完請求
たとえば、中古住宅の売買契約時において、雨漏りはないと示していたのに、雨漏りがある場合はメンテナンスを行うように請求できるということです。
なお、買主側の責任(確認不足など)で契約不適合が生じた場合は、追完請求を行うことはできません。
2.代金減額請求
3.催告解除
4.無催告解除
5.損害賠償
契約不適合責任の免責特約とは?
しかし、契約不適合責任を負わない旨の免責特約を設けることによって、この責任やリスクを回避する方法もあります。
ただし、契約不適合となる点について売主が知っていたのにも関わらず、買主に通知しなかった場合は信義則に反するため、契約不適合責任から逃れることはできない点には注意が必要です。
売主として、売却する不動産の内容および責任を負う範囲や期間を明確にして、買主に伝える誠意が大切です。
中古物件のトラブルで多いのは付帯設備に関するもの
設備の有無のみならず、設備の内容や状態(動作時に気になる点、不具合の状況、設備交換年月など)を細かく調査して、付帯設備表にまとめた上で、買主に説明して共有する姿勢は、後々のトラブル回避のために大切といえるでしょう。
売主が注意すべきポイント
法規にくわしい不動産会社を選ぶ
不動産会社を選ぶ際、まず物件査定を依頼することになりますが、より高い査定価格を提示してくれる会社が必ずしも良い不動産会社ではありません。
査定結果についての明確な根拠を示した上で、法規についての豊富な知識をもとに売買トラブル回避のためにどのような対応が必要なのか、親身になってアドバイスを行ってくれる不動産会社を選ぶようにしましょう。
契約不適合責任の通知期間を設定する
しかしそれでは、売却する不動産の内容および責任を負う範囲や期間を明確にして、買主に伝える誠意をもってしても、売主は物件を引渡した後、ずっとリスクにおびえなければなりません。
そこでポイントになるのが契約不適合責任を通知できる期間を決めることです。買主側が了解すれば自由に通知期間を定めることができますが、基本的には3か月が一般的です。不動産会社と相談しながら、通知期間を決めておきましょう。
インスペクションで物理的瑕疵を把握する
売主として、売却予定の不動産の状態を把握するためにも、インスペクションを実施しておきましょう。
インスペクションとは、建築士などの専門家が、不動産の劣化および不具合のある状況について客観的視点で調査を実施するものです。
インスペクションを行うことにより、売却予定の不動産について欠陥の有無や補修が必要な所やその時期などを把握することができるので、買主と正確な情報を共有できます。
瑕疵保険に入る
なお、契約時に買主が認識していた瑕疵については、補償の対象外となります。瑕疵保険に加入する場合も、建物の状況について正確な情報共有をしておくことは重要です。
不動産売却を決めたら、
一括査定サービスを利用して信頼できる不動産会社を見つけましょう!
不動産の一括査定依頼はこちらから無料

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
まとめ
しかし、売主として売却する不動産について十分に把握した上で、買主に引き渡すという当たり前のことが改めて明文化されたともいえます。
後々のトラブルを回避するためにも、売却予定の不動産および契約不適合責任についての知識を深めておきましょう。
不安になる前にプロに相談してみるのが、売却への第一歩です!
不動産の一括査定依頼はこちらから無料
約2,300社の中から1番条件の良い不動産会社が見つかる!

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
不動産売却の一括査定はこちらから
この記事の監修者

AFP/社会福祉士/宅地建物取引士/金融広報アドバイザー
日本社会事業大学 社会福祉学部にて福祉行政を学ぶ。大学在学中にAFP(ファイナンシャルプランナー)、社会福祉士を取得。大学卒業後、アメリカンファミリー保険会社での保険営業を経て、(マンションデベロッパー)にてマンション営業、マンション営業企画に携わった。その後、2008年8月より独立し、現在、自社の代表を務める。