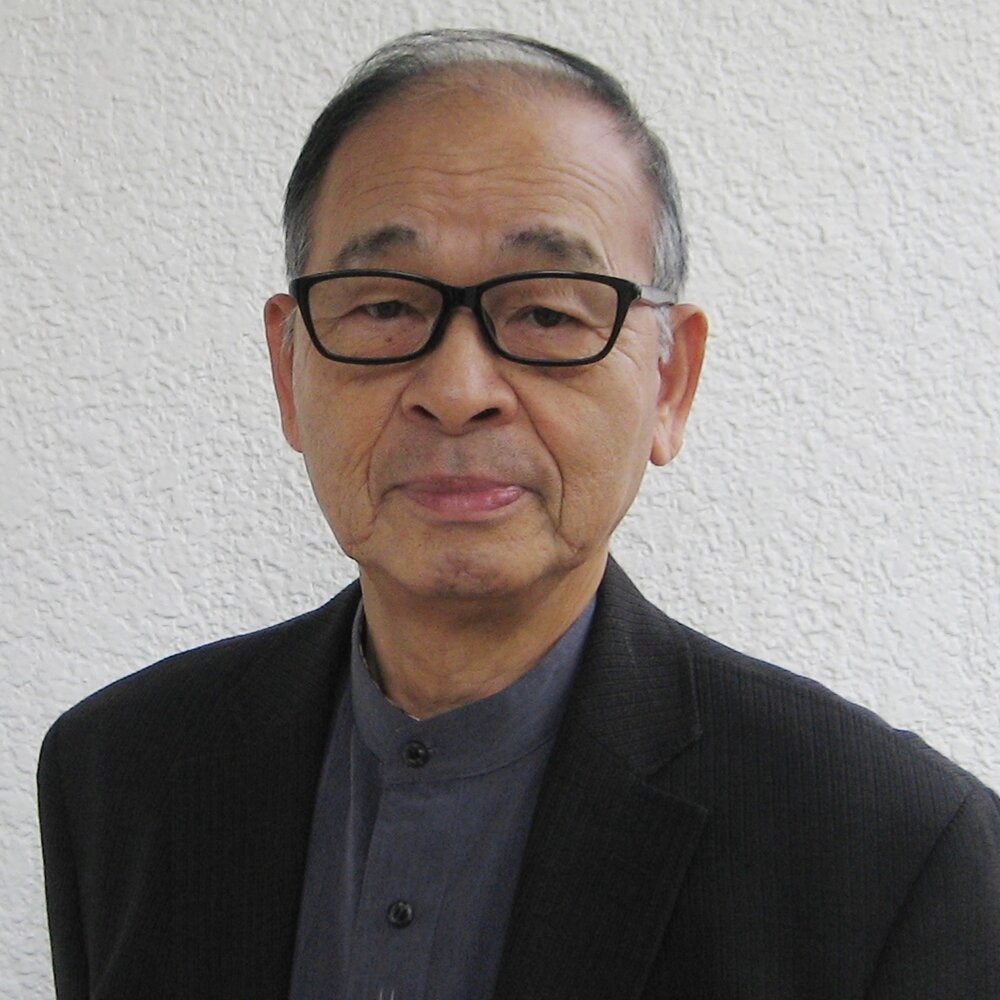- 譲渡型賃貸住宅は負担が少なくマイホームを取得できる新しい方法です。
- 通常通りマイホームを購入するよりもメリットが大きくデメリットが少ないと言えます。
- 譲渡型賃貸住宅ではこれまでの方法にとらわれず柔軟な思考で取り組みましょう。
土地活用プラン一括請求はこちら 無料
安心の提携企業がさまざまな土地活用プランをご提案致します

※ページ下部の「土地活用プラン請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
目次
譲渡型賃貸住宅とは
譲渡型賃貸住宅の仕組み

賃貸借契約が終了する時点で正式な譲渡契約を締結します。この時には大家さんは「売主」に、入居者は「買主」へと立場が変わります。譲渡時の代金については入居時の家賃設定にもよりますが、無償譲渡とすることが多いです。そのため買主には「贈与税」が課税されることになります。
通常の戸建て賃貸経営との違い
| 普通型賃貸 | 譲渡型賃貸 | |
|---|---|---|
| 家賃(月額) | 100,000 | 100,000 |
| 年間家賃下落率 | 0,967% | 0 |
| 賃貸期間 | 25年 | 25年 |

*年間下落率は総務省統計局「借家家賃の経年変化について」のデータに基づいています。
25年間の累積家賃収入は普通型と譲渡型で約323万円の差が生まれます。実際には普通型には空室期間もできるので差はもっと大きくなるでしょう。
また、戸建賃貸は空室になるとまったく家賃収入がなくなります。アパートと比べて戸建賃貸は空室リスクが非常に大きいと言えるでしょう。そのほか戸建賃貸の特徴などについては「戸建て賃貸経営」のページも参照してください。
譲渡型賃貸住宅投資が注目されている背景
持ち家よりも借家のほうが負担は少なく、30歳代以下では賃貸志向が高まっている傾向もあります。譲渡型賃貸住宅は家賃を支払いつづけることにより、将来引っ越すことなく持ち家にすることが可能であり、住宅ローンを借入することなくマイホームを持てるという大きなメリットがあるのです。
大家さんにとっては人口減社会になった今日、空室リスクはますます大きくなっています。譲渡型賃貸は長期にわたって入居が約束されたようなもので、安定経営が図れる有効な方法となってきています。
譲渡型賃貸投資のメリット
空室リスクが低い
譲渡型賃貸住宅は定期借家契約(普通借家契約の場合もあり)となるため、入居者は長期間居住する必然性が生まれます。途中退去になる場合はよほどの事情が起きない限りありえません。
よほどの事情とは、契約者が離職し収入状況が大きく変化するケースや、契約者が死亡し残された家族がそのまま居住することのできない状況に変わってしまうなどのことで、確率的には非常に少ないことと言えるでしょう。
家賃滞納リスクが低い
譲渡型賃貸住宅を選択して契約にいたる入居者の場合、収入がある程度安定しており将来も継続して安定する見通しがあるが、やむを得ない事情などで住宅ローンが借りられない人や借金をしたくない人などに限られます。そのため、家賃滞納がおこる確率が少ないと言えるでしょう。
立地条件が緩い
入居者によっては「畑付き賃貸」のように、田舎の物件を求めるケースもあります。入居者の希望に合わせた賃貸事業になるため、一般賃貸物件のように立地条件にこだわる必要はなくなります。
入居者募集・空室対策が不要
賃貸事業は空室を埋めるために多くの費用を投じることも多く、賃貸事業=空室対策と言ってもよい状況なのです。
出口戦略が不要
出口戦略とは賃貸物件を最終的に売却するか、自己使用に変更するかあるいは建物を解体して土地として売却するか、いずれかを選択することになります。
賃貸物件を売却するには入居者がいる状態で「オーナーチェンジ」するか、空室のまま売却することになります。売却のタイミングや売却先を探し出す活動など検討することも多くなるでしょう。
家賃下落リスクがない
普通借家契約では家賃の改定に関して、特約で認めないと定めた場合であっても、借地借家法第32条の次の条項が適用されます。
『建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。』
そのため譲渡型賃貸住宅では定期借家契約とするほうが望ましく、家賃下落リスクを低減できるのです。
譲渡型賃貸投資のデメリット
退去リスクはゼロではない
定期借家契約であっても、住宅の床面積が200m2未満で転勤などのやむを得ない事情であれば、入居者からの解約申入れが可能であることが借地借家法で定められています。申入れから1か月で契約は終了し、とくにペナルティを課されることもありません。
譲渡予約契約はあくまでも「予約」であって譲渡契約が成立してはいません。そのため賃貸借契約の途中解約により入居者が退去する場合、譲渡予約契約は効力を失い、違約金などの請求は無理があります。
譲渡型賃貸住宅を事業とする事例には「5年間の解約制限」を設けるケースもありますが、法的な拘束力には疑問があります。そのため退去リスクはゼロではありません。
安全なぶん利回りが低い
入居者にとって取得しやすい条件を優先することが重要であり、相場よりも利回りが低くなる傾向があります。普通型賃貸よりも空室リスクが低く滞納リスクも低いといったメリットの反面、利回りが低くなるデメリットがあることを認識しておきましょう。
売却益が望めない
賃貸期間中の家賃収入と必要経費やローン返済など、事業の収益性を事前に検証し事業の目的を達成できる事業計画が必要です。
契約年数を終えたら土地を失うことになる
入居時点では将来的な計画を立てて家賃設定を行いますが、長い賃貸期間により物件の資産価値が大きく変わり土地代が値上がりしていることもあります。
しかし、その場合でも当初の譲渡予約契約のとおり土地と建物を譲渡しなければなりません。普通型賃貸であったならもっと高く売ることができたのに、と後悔するケースがある可能性もあるでしょう。
取扱事業者が限られている
しかしながら住宅の賃貸借契約では、民法や借地借家法など法律的なことをクリアする必要もあり、賃貸借条件の調整も簡単ではありません。
そのため大家さんと入居者の条件調整を行うコーディネーターの役割が求められます。現在はこのようなコーディネートを行う事業者は少なく、地域の不動産会社で相談に乗ってくれるケースも少ない状況です。
譲渡型賃貸投資を始めるには
譲渡型賃貸投資の事業者例
| マリアージュ賃貸(特許出願中) | |
|---|---|
| 運営会社 | 有限会社ファーム建設 神奈川県横浜市港北区篠原町1187-6 |
【特徴】中古戸建住宅と中古マンションを中心に譲渡型賃貸投資事業を展開。入居希望者の希望エリアや希望条件をWeb上で情報発信し大家さんを募集しますが、大家さんは「マリアージュ賃貸」のFC会員となります。また物件を紹介してくれる不動産会社や、入居者を紹介してくれる不動産会社とのネットワークも構築しています。賃貸借契約は普通借家契約として締結しており、「マリアージュ賃貸」はオプションとしての位置づけになっています。
運営会社からは大家さんに対して「買取金額」が提示され、家賃収入に応じて毎年更新する方式(中古住宅の為、平均利回りは13%~16%)です。
平均家賃は7万~8万円、取得費とリフォーム費用の合計平均は700万円程度とのこと。万が一、大家さんが経営破綻した場合は、運営会社が買取して賃貸契約を継続させる方式になっています。
譲渡型賃貸投資の注意点
途中退去や有事の対応などの契約をよく確認する
また新築やリフォームをする場合に、工事費用に対し金融機関の融資を受ける場合は、返済期間を賃貸契約期間以内にする必要があります。
ほかの土地活用と比較検討する
それぞれにメリット・デメリットがあり、検討は慎重にかつ正確な情報に基づいて行う必要があるでしょう。「土地活用法まとめ」を参考にして検討するようおすすめします。
まとめ
・大家さんにとっては長期の入居を確保できる
・入居者にとっては支払う家賃が住宅取得のための資金に変わる
不動産投資や土地活用の手法は広がりをみせています。これまでの方法にとらわれず今後の賃貸ニーズを予測し、社会の変化に対応した投資手法が需要を生み、継続性の高い不動産投資を可能にすると言えるでしょう。
空室リスクなどを減らし、入居者の持ち家願望も満たす、
「譲渡型賃貸住宅」をご紹介します!
土地活用プラン一括請求はこちら 無料
安心の提携企業がさまざまな土地活用プランをご提案致します

※ページ下部の「土地活用プラン請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
この記事の監修者
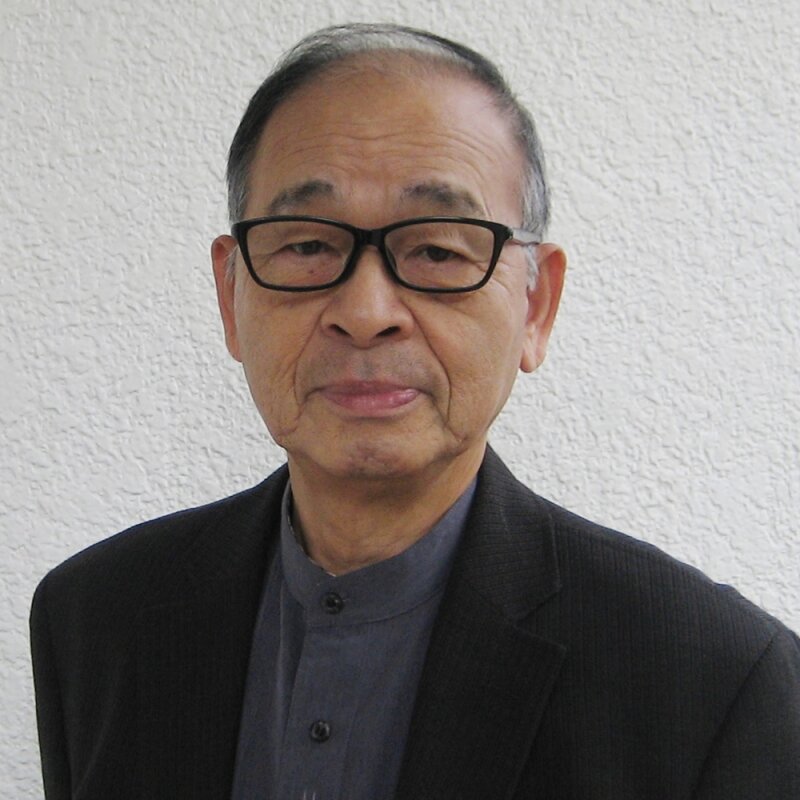
宅地建物取引士/一級建築士
宅建取引士・一級建築士として住宅の仕事に関り30年。住宅の設計から新築工事・リフォームそして売買まで、あらゆる分野での経験を活かし、現在は住まいのコンサルタントとして活動中。さまざまな情報が多い不動産業界で正しい情報発信に努めている。