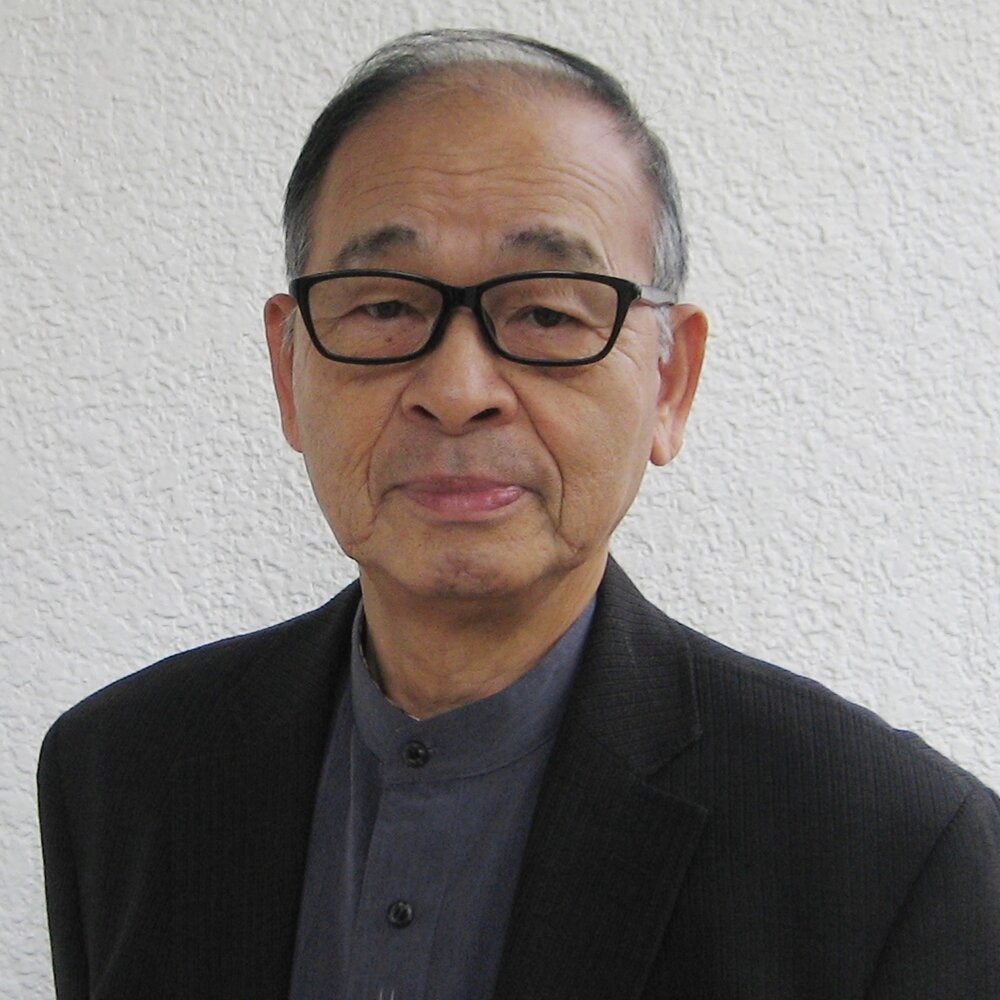- 投資効率の高い3階建て木造共同住宅ですが、メリットを生かすには緩和規定を満たす土地に建てる必要があります。
- まずは建設予定の土地に条件が見合っているかを確認しましょう。
- 施工会社の選定も成功のポイント。実績のある複数社のプランを比較するのがおすすめです。
土地活用プラン一括請求はこちら 無料
安心の提携企業がさまざまな土地活用プランをご提案致します

※ページ下部の「土地活用プラン請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
目次
投資効率のよい木造多層階賃貸住宅
最近では2階建て木造アパートよりも敷地を有効活用でき、投資効率がよくなる多層階の木造賃貸住宅が注目されるようになりました。今、なぜ木造なのか? 木造建築の現在を概観してみます。
木造建築が世界でも注目を浴びている
2017年にはカナダのバンクーバーに18階建てのビル「ブロックコモンズ」が完成し、大学の学生寮として使われています。使用した木材は2233立方メートル、耐用年数は100年以上と想定されます。削減できるCO2排出量は2432トンにも及びSDGsにも寄与する建築物となりました。
日本においても国土交通省の編集協力の下、一般社団法人 木を活かす建築推進協議会が「木造建築のすすめ」をリリースし、公共建築物などの大型建築物を木造で建築した事例を紹介しています。
木造3階建てが注目されている理由
さらに最近になり、建築材料として木材を活用することがサステナブルな社会の実現に寄与し、地域経済の活性化につながると期待されています。また、防火性の高い木材が実用化されるなど、木造建築に対する技術面の新しい試みも功を奏し、木造建築の規制が緩和されてきました。
このようなことから、木造3階建て共同住宅も耐火性や耐震性に優れており、賃貸住宅の有力な建築方法として見直されているのです。
3階建て木造賃貸に向いている土地とは
【条件1】建ぺい率60%、容積率150%以上の土地
容積率は、敷地面積に対する建物全体の面積(延床面積)の割合を言い、50~1300%の範囲で、これも都道府県または市区町村が都市計画で定めています。
一般的に、アパートなどの賃貸住宅は「住宅系」の用途地域に建てることが多いのですが、「商業系」や「工業系」の用途地域に建てる場合もあります。
敷地の有効利用を考えると、建ぺい率と容積率は大きいほうが望ましいでしょう。3階建てを建てるのであれば、住宅系の用途地域で厳しい規制のある「第一種低層住居専用地域」や「第二種低層住居専用地域」ではないほうがよいと言えます。
3階建て木造賃貸住宅には、建ぺい率60%以上、容積率は最低でも150%以上の土地が向いているでしょう。仮に単純計算すると、建ぺい率が60%であれば、3階建てにすると容積率180%までの建物を建てられ、容積率が大きいほうが敷地を有効利用できるわけです。建ぺい率や容積率のくわしいことはこちらの記事も参考にしてください。
【条件2】準防火指定地域の土地
しかし、商業系の用途地域は「防火地域」や「準防火地域」に指定されることがほとんどであり、防火性能の高い建物にしなければなりません。木造3階建てのアパートを建てる場合、防火地域と準防火地域とで大きな違いがあります。
建築基準法でアパートは「共同住宅」と定義される用途であり、3階建ての場合は原則「耐火構造」にしなければなりません。しかし木造建築の普及を目的とした政策により、防火地域以外の場合は「1時間準耐火構造」でも建てられるように緩和されています。
耐火構造と比べると1時間準耐火構造の建築コストは安く、3階建て木造賃貸を建てるなら、防火地域の指定のない地域か準防火地域までが望ましいと言えるのです。
【条件3】広い土地
しかしバルコニーや庇の設置などはコストアップにつながり、敷地は広いほうが建てやすいという面があります。
3階建て木造賃貸のメリット
高収益が狙える
また、3階建て共同住宅は本来、耐火構造としなければなりませんが、木造3階建ての共同住宅は本格的な耐火構造である鉄筋コンクリート造や重量鉄骨造よりもコストが安く、初期投資額を抑えることが可能です。その結果、2階建てアパートよりも収益性が高まるでしょう。
構造計算により安全性が担保される
つまり、木造3階建て共同住宅は必ず構造計算をしなければならないのです。逆に言うとその分、安全性を客観的に確認できるので、より安心感のある建物になります。
外観のデザインが多様である
入居者にとってもデザイン性の高さは付加価値となり、入居率を高める効果も期待できるでしょう。
節税効果が高い
建物の取得費は、損益計算において減価償却により毎年少しずつ損金算入でき、不動産所得から減価償却費を控除した残りの利益に課税されます。たとえば資産価格5,000万円の木造の建物と鉄筋コンクリート造の建物を比較すると、年間の減価償却費は次のようになります。
このように木造は鉄筋コンクリート造の約2倍の減価償却が可能で、節税効果が高くなるのです。
狭小地や変形地でも対応しやすい
そのため、変形地や狭小地でも敷地の形状に合わせた平面計画が可能です。また部材の搬入などもしやすいため、前面道路が狭く大型クレーン車が入れないなど、不利な条件の土地にも建築が可能です。
RC造・鉄骨造・SRC造より費用が安い
国税庁が公表している令和3年分の「地域別・構造別の工事費用表」で東京都のケースを見ると、以下のようになっています。
| 構造 | m2単価 |
|---|---|
| 木造 | 176,000 |
| RC造 | 320,000 |
| SRC造 | 338,000 |
| 鉄骨造 | 298,000 |
3階建て木造賃貸のデメリット
2階建てよりも工期が長い
さらに、工期が長いとアクシデントなどにより工事がストップする確率も高くなるので、竣工ギリギリに開業時期を設定しないよう、注意したいところです。
2階建てよりも建築費が高くなりやすい
軟弱地盤の土地ではボーリングを行ったり、杭の長さや本数が増えたりすることもコストアップの要因です。また工期が長い分、安全対策や工事管理の面でも経費がかかります。
施工会社が限られる
3階建て建築物の設計・施工を依頼するにあたっては、構造計算が必要となる建築物の施工経験がある会社が望ましいと言えます。構造計算を得意とする建築士がいる会社、または普段から構造設計事務所に多く依頼しているような会社でなければ、設計の段階でスムーズにいかない可能性があるのです。
設計は建築士事務所、施工は建設業者というように、設計と施工を別に依頼する場合であっても、3階建て以上の建築物を多く手掛けている会社のほうが安心できるでしょう。
入居者ターゲットが限定される
入居者ターゲットが限定されると顧客母数が小さくなるので、より厳密なターゲットマーケティングを行い、入居条件や物件企画を熟考しなければなりません。企画がうまくいかないと満室経営が難しくなり、3階建て共同住宅のメリットを生かせなくなってしまいます。
3階建て木造賃貸を建設する際の注意点
防火設備・避難設備(バルコニーなど)が必要
また、避難上有効なバルコニーの設置も義務付けられています。バルコニーには細かな構造基準と緩和基準があるので、条件を確認する必要があります。
建築コストが地域の賃貸需要に見合っているか
住戸プランや家賃設定がその地域と適合すれば、安定経営が期待できます。しかしコストが高いことから、事業計画における前提条件などに狂いがあっても計画の見直しが難しいのです。
ローンの借入期間に注意
返済期間はキャッシュフローに大きく影響するので、建築コストが高い分、返済比率が高くなることもあります。長期にわたるシミュレーションを行い、安定性の高い事業計画にすることが重要です。
3階建てが得意なビルダーか
計画している地域で実績のある会社を探すか、「土地活用プランの一括請求」などを活用して、慎重に施工会社を選びたいものです。
まとめ
耐震性や耐火性に優れた建物が木造で可能になった現在、大家さんにとっては収益性の高い賃貸経営もできますし、入居者にとっては木造のよさが感じられる付加価値もあります。木造3階建て共同住宅を検討する場合には、経験豊かな工務店やビルダーなどに相談するところから始めましょう。
世界的にも木造建築の需要が高まっています。
あなたの賃貸経営にも取り入れてみませんか?
土地活用プラン一括請求はこちら 無料
安心の提携企業がさまざまな土地活用プランをご提案致します

※ページ下部の「土地活用プラン請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
この記事の監修者
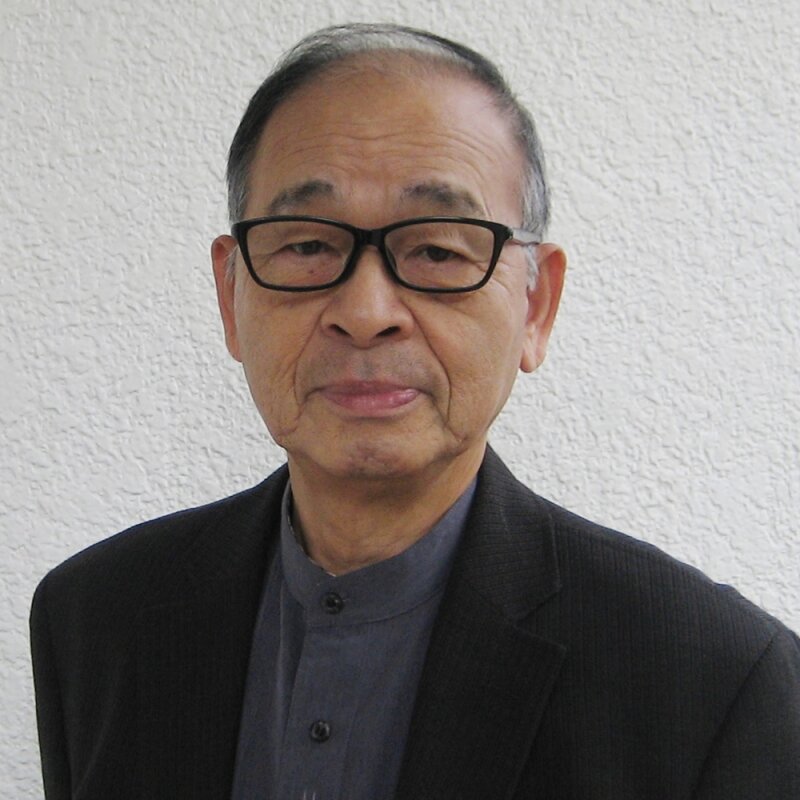
宅地建物取引士/一級建築士
宅建取引士・一級建築士として住宅の仕事に関り30年。住宅の設計から新築工事・リフォームそして売買まで、あらゆる分野での経験を活かし、現在は住まいのコンサルタントとして活動中。さまざまな情報が多い不動産業界で正しい情報発信に努めている。