- 不動産投資で耐用年数が重要なのは、融資~出口戦略にまで影響を及ぼすためです。
- とくに、金融機関は融資の返済期間を物件の耐用年数以上の期間に設定することを避ける傾向に…。
- 購入を検討している物件の耐用年数は必ず把握し、その上で投資計画を立てるようにしましょう。
目次
耐用年数とは
耐用年数は不動産投資を検討する際のとても重要な要素です。金融機関は融資の返済期間を物件の耐用年数以上の期間に設定することを避けます。
減価償却費の計算は適用する耐用年数を基礎としますので、結果納付する所得税の額に影響を及ぼします。減価償却費計算の基礎となる耐用年数は、納税者間の公平を期すため、構造、用途、細目別に指定されています。この税法で定めている耐用年数のことを法定耐用年数といいます。
建物構造別耐用年数
| 構造 | 法定耐用年数 | |
|---|---|---|
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 または鉄筋コンクリート造 | 47年 | |
| レンガ造、石造またはブロック造 | 38年 | |
| 重量鉄骨(骨格材4mm超) | 34年 | |
| 軽量鉄骨 | 骨格材3mm超4mm以下 | 27年 |
| 骨格材3mm以下 | 19年 | |
| 木造または合成樹脂造 | 22年 | |
不動産投資で耐用年数が重要な理由
融資に影響する
当然のことですが同じ金額の融資を受けても融資期間が短いほど、毎月毎年の返済額は多額になります。たとえば1,000万円を金利2%、返済期間30年で借入した場合の毎月の返済額は3.7万円程ですが、返済期間が20年になると5万円程、返済期間10年の場合は9.2万円程になります。
年間返済金額で比較すると、返済期間30年の場合44万円、20年の場合60万円、10年の場合110万円と大きな違いが生じます。融資返済を行っても投資収支がマイナスにならないかは、物件購入前に検討しておくべきことです。
減価償却に影響する
耐用年数が長くなるほど、一年あたりの減価償却費は減少します。減価償却費の大小はそのまま必要経費に含まれる金額の大小を意味し、納付する所得税の大小にも影響を与えます。
たとえば取得価額1,000万円の建物の耐用年数が10年であれば、償却率は0.1となり1年あたりの減価償却費は100万円となりますが、耐用年数が35年の場合、償却率は0.029となり1年あたりの減価償却費は29万円となります。
100万円-29万円=71万円の経費の差は、税率30%が適用される方の場合、納税額ベースで21万円変わることを意味します。
出口戦略に影響する
耐用年数を用いた減価償却費の計算方法
取得価額×定額法の償却率
上記算式中の「取得価額」とは、建物等の購入金額のことです。建物を購入するために他に費用が掛かっている場合、その金額もプラスします。たとえば不動産仲介会社に支払う仲介手数料や、売主に支払う固定資産税精算金等です。登記のための手数料や税金はプラスしなくても良いことになっています。
算式の「定額法の償却率」はWeb上でも情報収集することができます。下記リンクの情報などを参考になさってください。
一点ご注意点頂きたいのは、耐用年数や償却率など税法上の定数を確認したい場合、なるべく国税庁などの公的なサイトから情報収集することです。まれにですが税制改正などにより数値が変更されることがあるためです。
計算例で考えてみましょう。
| 投資物件 | 賃貸住宅用建物 |
|---|---|
| 取得価額 | 30,000,000円 |
| 耐用年数 | 47年 |
| 償却率 | 0.22 |
30,000,000×0.22=660,000円(1年分の減価償却費)
中古建物の耐用年数の計算方法
また適用する耐用年数について税務当局との見解の違いを避けたいこともあり、以下の簡便法により算定した年数を用いることが多いです。
【中古物件の耐用年数】
| ①法定耐用年数の全部を経過した資産 | 法定耐用年数×20% |
|---|---|
| ②法定耐用年数の一部を経過した資産 | 法定耐用年数-経過年数+経過年数×20% |
たとえば、鉄筋コンクリート造の賃貸用マンションを建築後10年経過後に取得した場合の耐用年数の計算は以下の通りとなります。
47年-10年+10年×20%=39年
中古物件の購入を検討する際は、経過年数を把握しなければ適正な耐用年数を算出できません。つまり精度の高い投資計画を立てることもできないわけです。
また、上記はあくまでも減価償却費を計算する際の見積耐用年数の計算です。金融機関が融資の返済期間を検討する際には、経過期間の20%を加味することはあまり一般的ではありません。ですから中古物件の取得に係る融資期間は、通常は、法定耐用年数-経過年数で算出される年数を基礎として検討されます。
減価償却に関する注意点
| 取得価額 | 2,000万円(うち土地代金1,000万円、建物代金1,000万円) |
|---|---|
| 耐用年数 | 10年(定額法償却率 0.1) |
土地建物を売却する際の税金は以下の算式により計算されます。
譲渡所得の金額=譲渡収入-(取得費+譲渡経費)
税金=譲渡所得の金額×税率(短期39.63%、長期20.315%)
算式中の取得費は、土地の場合取得価額を意味しますが、建物の場合取得価額から減価償却費を差し引いた売却直前の帳簿価額を意味します。計算例の場合、8年間の減価償却費は、1,000万円×0.1×8年=800万円となります。この建物の売却直前の帳簿価額は、取得価額1,000万円-800万円=200万円となります。
譲渡経費が掛からない前提で計算すると、上記計算例の譲渡所得の金額は、1,500万円-(1,000万円+200万円)=300万円となります。8年間所有しており、長期譲渡所得に該当することから、概算の所得税等の金額は、300万円×20.315%≒61万円ということになります。
毎年の減価償却費は、建物の帳簿価額から控除され、その建物を譲渡する時の譲渡所得税に影響するということは覚えておいてください。
耐用年数から見る!築年数別中古マンションの注意点
毎年の減価償却費>毎年の借入返済元金
となると通常は資金繰りが楽になる、ということです。
ここでの注意点は、減価償却費との大小比較を考えるのは、返済総額ではなく返済元金であることです。
また、償却費が返済元金よりも大きいといっても、なるべくその差は僅かであることが望ましいです。当初の償却費が大きいと、早期に減価償却が完了しその後の資金繰りが悪化するからです。
償却費>返済元金の状態でも計画上の資金繰りが厳しくなる物件は、利回りが低い、借入が過重、経費が多いなど、投資案件としてのバランスに問題が存在していることが考えられます。
築5年以下
金融機関からの融資期間も30年から35年の長期間、かつ土地代金まで含めた融資を受けられる可能性が高いです。償却費>返済元金の状態で長期間賃貸経営をできる事例が多いです。
こうした物件は長期保有に向いています。生命保険契約の替りとして、将来の年金的な収入確保のため、などベースとなる財産形成を目的とした投資に適しているでしょう。
このような物件でよく見られるのは、不動産所得で赤字を捻出し、給与所得などとの損益通算で所得税還付を受けるスキームです。
しかし土地の購入価額を借入金で賄っている場合、不動産所得が赤字でも損益通算の対象となる金額が制限されます。販売業者から説明されたほどの所得税還付効果を得られない場合もあります。
容認できるリスク範囲・年間キャッシュアウトを冷静に分析し、場合によっては売却処分も選択肢の一つとなります。
築15年前後
この経年の物件購入を検討する場合、売りに出された背景を確認しておくことは重要です。新しい賃貸住宅の建築や会社・学校の移転などによる近隣の賃貸市場の変動、募集資料の想定利回りと近隣賃料相場に矛盾がないかなどは要検討です。
経過年数15年の鉄筋コンクリート造の住宅の耐用年数は35年、重量鉄骨造22年、木造10年になります。金融機関からの融資期間も、耐用年数に応じた期間となります。木造以外は建替えを検討するのはまだ早い時期です。一部でも土地代金として自己資金を拠出できないと、賃貸経営時のキャッシュフローは苦しくなります。
空室率が低く利回りの良い物件は長期保有に向きますが、駅近など利便性の高い優良な土地であれば短期的な売却益を狙えるかもしれません。
築25年以上
経過年数25年の鉄筋コンクリート造の住宅の耐用年数は27年、同重量鉄骨造14年、木造4年になります。木造の物件では余り融資は期待できません。利便性の高い土地であれば、建て替えを見越した投資戦略も選択肢にはいります。土地の属性が優良なものでない限り、短期的な売却益を見込んだ投資と位置付けるのが望ましいです。
築25年以上経過している物件は資金面で融資に頼れない部分が多く、また修繕費など不測の支出も増えるので、賃貸経営にある程度経験を有し、自己資金に余裕のある方向けとなります。

| 【PR】RENOSY |
|---|
|
選ぶべき投資用物件は目的によって異なるため、利回りだけで判断できるものではなく、不動産投資初心者にとって物件選定はつまづきやすいポイントです。物件選びで失敗しないためには、良い不動産会社選びがとても重要。「RENOSY不動産投資」は、物件情報を独自のデータベースに蓄積し、投資価値の高い物件をAIを使って効率よく厳選し、提案してくれるサービスを提供しています。不動産投資初心者の方や物件選びに自信のない方にとっては心強いサービスです。
初心者だけど効率よく不動産投資を始めたい方、まずは無料の資料を確認してみませんか? 無料の資料を見てみる
※「RENOSY」へ遷移します |
まとめ
物件購入検討時には対象物件の耐用年数を必ず把握しましょう。その上で投資計画を立てるようになさってください。ご自分での計画立案が難しい場合、是非不動産のプロや税理士の力を借りてください。不測の事態を極力排除した精緻な投資計画を立て、堅実に財産形成をしていきましょう。
物件の耐用年数を見定めて
投資計画を組むことが成功の鍵です。
この記事の監修者

税理士
会計事務所に勤務しつつ平成16年税理士試験に合格。税務コンサルタント会社にて金融機関をサポートする業務の中、資産税業務の経験を積む。平成22年税理士法人シン総合会計設立。主に中小企業の会計税務支援を中心に、事業承継、資産税業務にも従事。不動産会社の税務相談会相談員、金融機関のセミナー講師等に携わる。

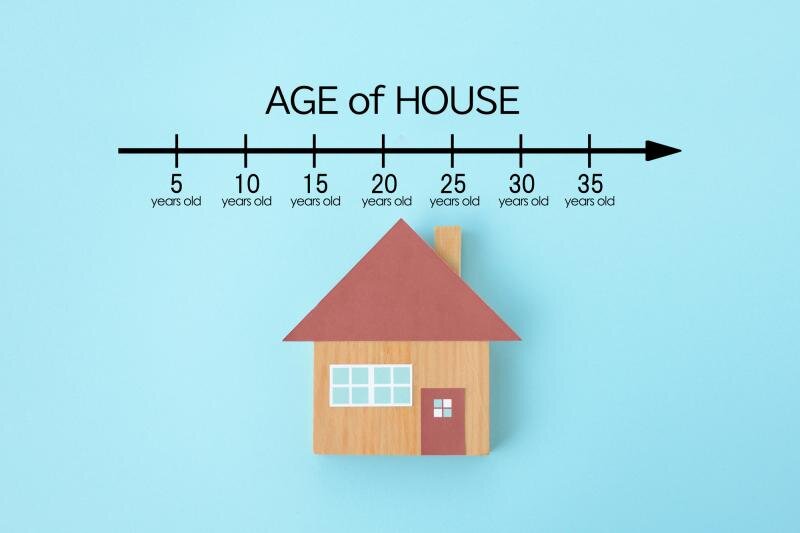

耐用年数が短い建物ほど「所得税の節税効果がある」ということになります。投資用物件を選ぶ際はぜひ耐用年数に着目してみてください。